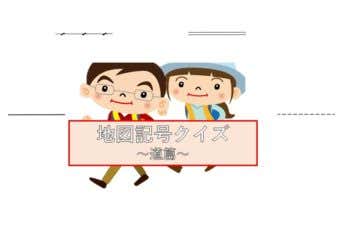⑲滝

川の水の流れが落下するところを滝といい、高さが5m以上で常時水が流れている滝を示しています。幅20m以上の滝は滝(大)の記号で表記します。川や沢のあるところで目にする記号です。
⑳池

自然・人工問わず、池や沼は25m×25m以上の大きさで常に水をたたえているものが記号で表示されます。山上にも池はあり、現在地のだいたいの把握に活用できるでしょう。
㉑湿地

湿地は水を含んだ土地のことで、75m×75m以上、または50m×125m以上の大きさのものが記号で示され、荒地の記号が重なって表示されていることもあります。
㉒川

川は水色で塗られた幅のある線や青の一本線で表示され、幅も川幅にならって示されています。ただし、山中にあり、季節によっては涸れることもある小さな沢までは表示されていません。
㉓万年雪

万年雪と呼ばれる地図記号で、一年中雪や氷が残っているエリアや雪渓にも使われることがあります。
大きさは大小様々ありますが、この記号で示されるのは9月に50m×50m以上残っているものです。一部の高山で出会う以外は滅多に見かけることはなく、気候によって地図に記載されている境界が違う場合があります。
まとめのクイズでチェックしよう
【5】道に関する記号

道を表す記号は登山で最もよく活用する記号で、主な登山道は徒歩道で示されています。しかし、道の様子は様々で、道と道の分岐が実際とは位置がズレていたり、実際には存在しないといった場合もあるので注意も必要です。
㉔徒歩道

道幅が1.0m未満の道を表し、登山道はこの徒歩道で表されることが多いのが特徴です。
ただ、整備された道や踏み跡が分かりにくい道など、いろいろな種類の道があります。最新の登山用地図やガイドブック等で道の様子を確認しておきましょう。
㉕幅員3.0m未満の道路

横幅が1.0m以上3.0m未満の軽車道を表します。登山道へ入るまでの林道などがこの軽車道で表されることが多く、舗装されている場合もあれば未舗装の道もあり。
㉖一車線道路

一車線の道路を表し、舗装された道であることが多いのが特徴です。大抵の場合、こうした一車線道路からさらに徒歩道や軽車道が分岐して登山口へと繋がっていますが、中には道路脇にいきなり登山口があることも。
㉗索道(ロープウェイ)

ロープウェイのゴンドラやリフトのなどの車体をぶら下げるケーブルが通っていることを示しており、スキー場がある山やロープウェイの架けられた山で目にできます。
ロープウェイ周辺が開けていれば、遠くからでも見えて現在位置を把握するためのよい目印となるでしょう。
まとめのクイズでチェックしよう
目立つけど地図に表現されないものも

石を積み上げたケルン。よく登山中に見かけますよね。山頂や稜線、登山道の分岐付近などで積み上げられて目立っていますが、地図に表記されていないので地図読みのナビゲーションとしての機能は薄いといえます。
地図読み最初のステップ、地図記号

登山に必要な地図記号を種類別にみてきましたが、地図記号の指し示すもののイメージが掴めたでしょうか?まだ今一つ記号とイメージが結びつかない人は、もう一度見返してみてくださいね。
地図記号を見たときに、すぐにその記号が表すもののイメージができたなら、地図記号もマスターです。そんなあなたは、復習も兼ねてこちらのクイズに是非挑戦してみてください!