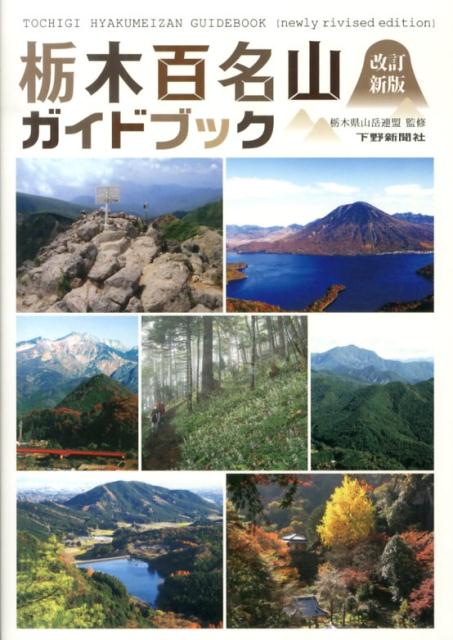アイキャッチ画像出典:PIXTA
栃木には日本百名山がなんと4座もある!

栃木県には百名山に選ばれた山も多く、とくに日光周辺は2,000m級の高山が楽しめる人気の山岳エリア。都心からのアクセスもよく、週末を利用して気軽に登山を楽しむことができます。
また、観光スポットや温泉も多く、登山の後に楽しめる要素も。今回は、百名山に指定されている栃木の山を難易度別にご紹介します。ご自分のレベルに合わせて安全に登山を楽しみましょう。
栃木県 山のグレーディングを参考にしよう!

山のグレーディングとは、登山経験の少ない初心者や中高年登山者などによる山岳遭難事故を防止するために定められた、登山難易度の指標。栃木県の主要な登山ルートが、体力レベル・技術レベルによってグレード分けされています。登山者に求められる技術や能力が分かりやすくまとめられているので、自分のレベルに合ったルートの選択が可能。山のグレーディングを活用して、自分のレベルにあった山に登りましょう。
紹介する栃木の山
1.那須岳(※)
2.男体山(※)
3.日光白根山(※)
4.皇海山
5.女峰山
県境に位置する山もありますが、今回は栃木県側から登れるコースをご紹介。1、2の山は日帰り可能ですが、3~5の山はロングコースとなっています。自身の体力や技術レベルを考慮し、無理のない計画を立ててください。
※の山は活火山です。現在の活動状況を必ず確認しましょう。
気象庁|公式サイト
那須岳 【難易度★★】

那須岳(別名:茶臼岳)は、栃木県北部に位置する標高1,915mの山。山頂からはモクモクと白い火山ガスが上がり迫力を感じさせます。
山頂付近はゴツゴツとした岩肌ですが、秋になると中腹から裾野にかけて鮮やかな紅葉で彩られる様は圧巻。茶臼岳とともに「那須岳」として百名山に選定されている朝日岳、三本槍岳へ足を伸ばす縦走コースが人気です。
おすすめ登山コース

歩き始めは緩やかな勾配でとても歩きやすいコース。朝日岳へ向かう際は、急登の鎖場やトラバース箇所もあるので注意して進みましょう。天候に恵まれれば日光白根山や男体山といった周辺の山々を一望できます。爽快感のある稜線歩きを堪能しましょう。
最高点の標高: 1896 m
最低点の標高: 1372 m
累積標高(上り): 1703 m
累積標高(下り): -1703 m
- 【体力レベル】★★★☆☆
- 日帰り
- コースタイム:6時間20分
- 【技術的難易度】★★★☆☆
- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要
・地図読み能力が必要
登山のための情報
【登山口へのアクセス】
■クルマの場合
東北自動車道「那須」IC−県道17号−那須ロープウェイ山麓駅
■公共交通の場合
JR「那須塩原」駅−関東自動車バス 那須線乗車−「那須ロープウェイ」バス停下車
関東自動車|路線バス
その他のコース情報
茶臼岳だけなら、ロープウェイ利用で1時間程度で登頂できます。初級者はこちらがおすすめ。
那須ロープウェイ|公式サイト
昭文社 山と高原地図 那須・塩原
男体山 【難易度★★★】

男体山は栃木県の中西部に位置し、日光・中禅寺湖を見下ろす標高2,486mの山。毎年5月5日に山開きが行われ、年間を通して多くの登山者が訪れます。周辺は歴史的な社寺や温泉も多いため、観光と合わせて予定をたてるのもおすすめです。
おすすめ登山コース

男体山への登山道はよく整備されていますが、急登や岩場が多く登り堪えのあるコース。山頂からは中禅寺湖を一望できます。下山を三本松方面へ下ると総距離約15㎞のロングコースに。志津乗越までは、急傾斜のザレ場や藪こぎして進む箇所もあるため注意して進みましょう。
最高点の標高: 2458 m
最低点の標高: 1278 m
累積標高(上り): 2392 m
累積標高(下り): -2275 m
- 【体力レベル】★★★☆☆
- 日帰り
- コースタイム:7時間45分
- 【技術的難易度】★★★☆☆
- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要
・地図読み能力が必要
登山のための情報
【登山口までのアクセス】
■クルマの場合
東北自動車道「宇都宮」IC−清滝バイパス−日本ロマンチック街道−国道120号−二荒山神社入口
■公共交通の場合
各線「日光」駅−東武バス 湯本温泉行き乗車−「二荒山神社中宮祠」バス停下車
東武バス|運賃・経路
その他のコース情報
ピストンコースならもう少し難易度が下がります。初級者はこちらがおすすめ。
日光白根山 【難易度★★★★】

日光白根山は、栃木県日光市と群馬県片品村の境に位置し、火山群に属する標高2,578mの山。毎年夏になると、シカイワカガミ、ハクサンシャクナゲなど多くの高山植物が登山者を出迎えてくれます。エメラルドグリーンに輝く五色沼も絶景ポイントのひとつ。
おすすめ登山コース

群馬県側からもアクセス可能ですが、今回ご紹介するのは栃木県側からのコースです。コースタイムが9時間超となるため、早朝アタック開始もしくは避難小屋で1泊するのがおすすめ。山頂からは360度広がる大パノラマを存分に味わうことができます。
最高点の標高: 2553 m
最低点の標高: 1488 m
累積標高(上り): 2097 m
累積標高(下り): -2097 m
- 【体力レベル】★★★★☆
- 日帰りもしくは1泊2日
- コースタイム:9時間35分
- 【技術的難易度】★★★☆☆
- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要
・地図読み能力が必要
登山のための情報
【登山口へのアクセス】
■クルマの場合
関越道「沼田」IC−国道120号−湯元温泉
■公共交通の場合
各線「日光」駅−東武バス 湯元温泉行き乗車−「湯元温泉」バス停下車
東武バス|運賃・経路
宿泊地
山中で1泊する場合には、五色沼避難小屋の利用となります。トイレはないので、携帯トイレを持参するなどしましょう。
その他のコース情報
初級者は群馬県側のロープウェイを利用して登るのがおすすめです。
皇海山 【難易度★★★★★】

皇海山(すかいさん)は、栃木県日光市と群馬県沼田市の県境に位置する標高2,144mの山です。栃木県側から登るコースは、「栃木県 山のグレーディング」で最高難度。訪れる人が少なくとても静かな山の中で、原始的な自然美を感じることができる山でもあります。
おすすめ登山コース

日本百名山を選定した深田氏が登ったとされるこのコースは、上級者向けの難易度の高いコース。細い尾根の急登や下り、背の高い笹薮の中を進む箇所もあります。距離も長いため、事前の情報収集は念入り行い余裕を持ったスケジュールを立てましょう。
最高点の標高: 2105 m
最低点の標高: 812 m
累積標高(上り): 5641 m
累積標高(下り): -5641 m
- 【体力レベル】★★★★☆
- 1泊2日
- コースタイム:14時間35分
- 【技術的難易度】★★★★☆
- ・岩場、雪渓を安定して通過できる技術が必要
・ルートファインディングの技術が必要
登山のための情報
【登山口へのアクセス】
■クルマの場合
東北道「宇都宮」IC−日光・宇都宮道「清滝」IC−国道120号−国道122号−県道293号−銀山平
■公共交通の場合
わたらせ渓谷鐵道「通洞」駅−タクシーにて銀山平へ
わたらせ渓谷鐵道|公式サイト
宿泊地
山中で1泊の際は「庚申山荘」を利用します。ハイシーズン以外は無人の小屋ですが、トイレ・洗い場・布団があります。食事は持参しましょう。
予約など詳細は国民宿舎かじか荘まで。
その他のコース情報
初級者は群馬県側の皇海橋からの登山がおすすめです。
昭文社 山と高原地図 赤城・皇海・筑波
昭文社 山と高原地図 赤城・皇海・筑波
番外編:二百名山 女峰山

女峰山(にょほうさん)は栃木県日光市の北側、男体山の北東約7㎞の地点に位置する標高2,483mの山です。女峰山は二百名山に指定されており、百名山の山々にも劣らない人気を誇る栃木県の名峰。古来より、山岳信仰の場としても多くの人に親しまれてきました。
おすすめ登山コース

スタート地点は日光霧降高原。6月中旬~7月にかけては鮮やかなニッコウキスゲが辺り一面に広がります。赤薙山から先はアップダウンが多くなり、岩場や木の根が張り出した箇所もあるため足元に注意して進みましょう。長時間のコースとなるため、早朝からアタックするか1泊して登るのがおすすめです。
最高点の標高: 2429 m
最低点の標高: 1340 m
累積標高(上り): 1520 m
累積標高(下り): -1520 m
- 【体力レベル】★★★☆☆
- 日帰りもしくは1泊2日
- コースタイム:10時間
- 【技術的難易度】★★★☆☆
- ・ハシゴ、くさり場を通過できる身体能力が必要
・地図読み能力が必要
登山のための情報
【登山口へのアクセス】
■クルマの場合
日光宇都宮道路「日光」IC−県道169号−霧降高原
■公共交通の場合
各線「日光」駅−東武バス 霧降高原または大笹牧場行き乗車−「霧降高原」バス停下車
※運行は4月~11月下旬の期間
東武バス|運賃・経路
その他のコース情報
「栃木百名山」も制覇しちゃう?
山好きの皆さん、”栃木百名山”なるものをご存知でしょうか?これは栃木山岳連盟が定めた栃木県内の登山におすすめの山100選です。200m級の低山から2,000m級の高山までを網羅。県内の様々なエリアの山が紹介されています。皆さんも”栃木百名山”を制覇してみませんか?
栃木百名山ガイドブック
週末は栃木の山から絶景を堪能しよう!

季節によってさまざまな表情を見せてくれるのも栃木の山の魅力。山頂から見渡す周辺の山々や湖は絶景です。登りごたえのある山々でパワーをチャージした後は温泉で汗を流し、美味しいお酒でリフレッシュ。皆さんも、一度味わったら”栃木の山”の虜になってしまうこと間違いなしですよ。
【登山時の注意点】
・登山にはしっかりとした装備と充分なトレーニングをしたうえで入山して下さい。足首まである登山靴、厚手の靴下、雨具上下、防寒具、ヘッドランプ、帽子、ザック、速乾性の衣類、食料、水など。
・登山路も複数あり分岐も多くあるので地図・コンパスも必携。
・もしものためにも登山届と山岳保険を忘れずに!
・紹介したコースは、登山経験や体力、天候などによって難易度が変わります。あくまでも参考とし、ご自身の体力に合わせた無理のない計画を立てて登山を楽しんで下さい。