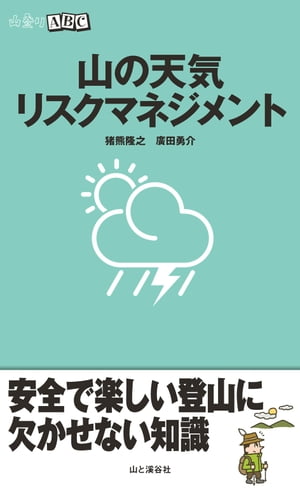アイキャッチ画像提供:廣田さん
登山のスキルを高めたい!そんなときは“山のプロ”にお任せ
登山を続けていると、「もう少し難易度の高い山に挑戦したい」「山のいろんな楽しみを味わいたい」という想いがわいてくるもの。実現のためには知識や技術の習得が欠かせません。
登山に詳しい人が身近にいない場合は、ガイド登山を依頼したり、講習会に参加したりするのもひとつの手です。必要なスキルはもちろん、その山や土地の歴史、植生についても学ぶことができるので、山の楽しみ方が広がります。
そうはいっても、誰にお願いしたらいいのか、どんな講習会に参加したらいいのか悩んでしまうことも。
そこで当企画では、自分の目標や目的、趣味趣向にあったガイドさんを見つけられるよう、さまざまなタイプのガイドさんにフィーチャー。今回は、プロカメラマンとしても活動し、YAMA HACKでもフォトトレッキングの楽しみを紹介してくれた廣田ガイドを紹介します。
廣田 勇介(ひろた ゆうすけ)

提供:廣田さん(法螺貝を奏でる廣田さん)
廣田勇介ガイド|ホームページ
日本固有の古から続く山とのスタンスを、現代へ伝えたい

提供:廣田さん(日本を代表する2人の登山家が成し遂げた「天岩戸注連縄神事」)
2021年12月、宮崎県高千穂町にある天岩戸神社のご神体である天岩戸にしめ縄を張る「天岩戸注連縄神事」が執り行われました。
天岩戸は神話以来、禁足地として永らく人跡未踏でした。近年、聖地として整備し、しめ縄を張る計画が立てられましたが、急峻な断崖にあるため計画は失敗。最後の頼みとして登山家に声がかけれらました。
これを実現したのが、日本人初の8,000m峰全14座登頂を成し遂げた登山家・竹内洋岳さんと石井スポーツ登山学校校長でもある国際山岳ガイド・天野和明さんという2人の日本を代表する登山家。
そしてこの2人を「現代の山伏」として招聘し、記録映像の撮影など影で支えた仕掛人こそが、今回ご紹介する廣田勇介ガイドなのです。
日本古来の名山の魅力を伝えたい

提供:廣田さん(先鋭的なクライミングやピークハント以外にも日本古来の山の楽しみ方があると語る廣田さん)
現代の日本で人気がある山の多くは「日本〇〇名山」「〇〇百名山」などが冠せられた山。しかし廣田さんは、それ以外の山々にも、ある切り口から観ることで感じ取れる魅力があると言います。
修行ではなくリフレッシュのための「山岳お遍路」

提供:廣田さん(伝統的な巡礼登山のスタイルである白装束に身を包んだ廣田さん)
日本独自の山岳信仰と言えば、1,300年以上の歴史を持つ修験道が代表的。修験者(山伏)が修行の場として歩いた山が、現在でも日本各地に存在しています。
けれども廣田さんが提唱する巡礼登山は、その伝統をそのまま再現するのではなく、より現代にマッチしたスタイルかもしれません。
活動の様子を拝見!
ここまでをご覧いただくと、廣田さんは「日本の歴史・文化を重んじる人」と言う印象を持つと思います。しかし実際は、それだけに留まらないインターナショナルな活動を展開しているガイドなのです。
山岳お遍路はプリミティブな日本の登山スタイルの現代版

提供:廣田さん(山岳お遍路のガイドをする廣田さん)
山そのものを神様として崇め、その神様に近い場所で祈りを捧げるために山に登る「登拝」は、古来から続く日本独自の登山スタイル。
その山にまつわる伝説・伝承を聴きながら、その山の歴史的バックグラウンドを学びながら歩くことで“単なるピークハント”だけに留まらない日本ならではの登山の醍醐味を体感することができるのです。
廣田さんの登山の原点……沢登りで自然と触れ合う

提供:廣田さん(廣田さんが「総合充実登山」と呼ぶ沢登り)
後にご紹介しますが、本格的な登山を始めたばかりの廣田少年が熱中していたのが奥多摩での沢登り。
廣田さんは沢登りのことを「総合充実登山」と呼んでいます。クライミングから読図まで様々な登山スキルが要求されるアクティビティだからこそ、経験豊富なガイドと臨みたいと言うお客様が多いそうです。
日本の山の魅力を世界に発信!インバウンド(訪日外国人観光客)向けガイド

提供:廣田さん(日本ならではの山の魅力を教えてくれる廣田さんのガイディングは大好評)
洋楽好きの母親が唄う英語の歌がいつも家にこだましていたという廣田さん。自然と自分からも勉強するようになり、なんと英語も堪能です。2022年現在は新型コロナウイルスの影響で休止状態ですが、インバウンド(訪日外国人観光客)を案内することも多いそうですよ。
東洋的なエキゾチックイメージを抱いて日本を訪れる人々、特にキリスト教文化で育った欧米豪からの観光客の興味をそそる日本ならではの山岳信仰や歴史・文化の解説を交えながら登山をサポートできるのも、廣田さんならではですね。
世界有数の豪雪地帯・日本の雪をとことん楽しんでもらうバックカントリースキーガイド

提供:廣田さん(廣田さんのホームグラウンドでもある後立山連峰でのバックカントリースキー)
実はカナダでのバックカントリースプリットボード(*)ガイド資格を最初に取得したガイドのひとりでもある廣田さん。つい数年前までは、カナダでのバックカントリーガイド業務も行っていました。
日本に帰国後も冬はバックカントリーガイドがメイン。これまた世界有数の豪雪地帯を有する日本に魅力を感じて訪れるインバウンドの参加者が多いそうです。
中にはカナダ在住の知己のガイドに「日本に行ったらユースケを訪ねろ」と言われて来る人も。必然的に長期滞在となるため、冬はほとんど休みなし……という年も珍しくなかったそうです。
*スプリットボード:スノーボードが真ん中で2つに分かれスキーとしても使用できる主にバックカントリーで使用される板
何と独学!写真家としての感性のルーツは「雪との対峙」

提供:廣田さん(「銅像写真家」でもある廣田さんならではの作品には独自の世界観が)
プロカメラマンとして登山雑誌から依頼されてルポ撮影も担当する廣田さんですが、自身のライフワークとして撮影しているのは、ガイド業務も行う信仰の山や山岳スキーがモチーフ。加えて歴史好きが高じて、ここ数年は日本各地にある偉人の銅像を撮り歩いているそうです。
そんな廣田さんですが何と写真は独学、しかしその感性のルーツはやはり山にありました。バックカントリースキーは常に雪崩の危険性と隣り合わせ。常に山を観察して、ほんのわずかな変化から雪崩の予兆を認識することが生命を守ることにつながるため、そのトレーニングは欠かさなかったそうです。
山岳気象の書籍で雪崩と気象の関係を執筆したこともある廣田さんだからこそ、自然を緻密に観察する眼が自然と養われたのですね。
山登りABC 山の天気リスクマネジメント【電子書籍】
山の天気の基礎知識と、リスク対処法を入門者にもわかりやすく解説したポケットガイド。
著者は山岳気象予報士の猪熊隆之さんと、雪崩の専門家としても活躍する山岳ガイドの廣田勇介さん。
・ウェブサイトによって、天気予報が違う。どっちを信用したらよい?
・昨日まで好天の予想だったのに、山行直前になって天気予報が急に悪くなった。山行を見合すべき?
そんなリアルな「山の天気」の疑問にお答えするのが本書です。明日からの山行に、「即」応用できる、実践的な天気の知識を集めました。
好きなことにとことん没頭……その根源は「格好いい!」という直感!?
廣田さんが登山を始めたきっかけや青春時代、そして山への想いについて伺いました。そこにはこれまでご紹介してきた多彩な活動の根源が垣間見える、様々なストーリーが。
東京に残された自然の中で遊んだ少年時代

提供:廣田さん(放課後は毎日焚き火をしていたという廣田さん)
——山や自然に親しんだきっかけを教えてください。
父親がキャンプ好きで、家族旅行と言えば旅館でなくテントに泊まっていました。今と違って炊事場や水場もないキャンプ場がほとんどでしたが、全国各地に出かけましたね。
あとは焚き火です。出身地の大田区は湾岸地域に埋立地が多かったのですが、中学生の頃までは利用の目処が立たずに放置されてジャングルのようになっていました。
そんなワイルドな場所で、放課後は毎日のようにブラックバス釣りと焚き火をしていましたね。
——本格的な登山はいつ頃から始めたのですか?
高校時代に山岳部に所属してからです。今の活動と違いオーソドックスで泥臭い、いわゆる昔ながらの登山スタイルでした。
週末はほとんど奥多摩の山に入り浸って、沢登りや焚き火を楽しんでいましたね。
大学では他校の学生と登山に行くことに制約があった山岳部には入らず、高校時代からの仲間と登山を続けていました。
作家志望から一転、カナダに渡ってクライミングとバックカントリースノーボードの武者修行

提供:廣田さん(ガイド修行をしたカナダBC州のBaldface Lodge )
——日本大学藝術学部に在籍されていたそうですが、元々はガイドでなく芸術家になりたかったのですか?
もともと読書が好きで、山の文学を執筆する作家になりたかったんです。そこでコピーライターなど“言葉”を職業とする人を多く輩出している文芸学科に入学しました。
ただ途中で挫折してしまって(笑)。
そこで大学を1年間休学して、カナダにあるヤムナスカ登山学校というスクールに入ったんです。
——文学から一転して、登山を本格的に学ぼうと思ったきっかけは?
高校以来ずっと登山は続けていて、縦走や雪山も経験しました。
ただ登山者として次のステップに進むためには、クライミングをきちんと学ばないといけないと思って。
そこで調べたところ、山岳雑誌の記事でスイスとカナダに長期間登山を学べる学校があるのを見つけたのです。
アルバイトでお金を貯めて、ロッキー山脈があるバンフ国立公園の隣にあるキャモアという街で1年間生活しました。
——バックカントリースノーボードもカナダで?
クライミングに必要なロープワークなど、ひと通りの技術はヤムナスカ登山学校でマスターしましたが、それだけでは十分な経験やスキルにはならないと思って。
卒業した後もカナダに残って、各地を旅しながら雪山に登ってはスノーボードで滑降していましたね。

提供:廣田さん(スノーボードで華麗に雪山を滑降!)
——そのバックカントリースノーボードが、今もガイド活動の大きな柱になっているのですね。
日本に帰国してからは登山用品店でアルバイトしていたのですが、そこで販売していた『POWDER』というスキー雑誌に載っていた、山岳登攀の対象になってきた山を滑降する写真がすごく格好よくて。
「これが自分のやりたいことだ!」と直感して、そこからは人生のすべてをバックカントリースノーボードに捧げて来ました(笑)。
——趣味ではなく、職業ガイドとしてバックカントリースノーボードに取り組むきっかけは?
長野県白馬村に現在でも日本のバックカントリースキーを牽引しているガイドクラブが設立されて、そこで修行したくて門を叩いたのがきっかけです。
それ以来、冬は白馬村でバックカントリーガイド、夏は全国の山々のガイドや海外遠征、という日々を送っていました。
信仰登山の魅力を教えてくれた「富士山」

提供:廣田さん(現代でも山岳信仰が息づく富士山では伝統的な祭事が今も開催されています)
——もうひとつの活動の柱である信仰登山への興味はいつから芽生えたのですか?
バックカントリーガイドができない夏にガイドとしてメインで案内していたのが富士山、350回くらいは登っていますね。
そこで富士講と言われる山岳信仰の信者さんたちとすれ違うことが度々あって。
当時は北米かぶれで髪もブルーやピンクに染めていた自分からすると、白装束に身を包み金剛杖を突きながら経文を唱えて登っている姿がメチャメチャ格好よく新鮮に見えたんですね。
それをきっかけに、全国の霊山を調べたり取材するようになりました。
——「格好いい!」というインスピレーションが、活動の源になることが多いのですね!
同じ時期に富士山で活動していたガイドには、そこで資金調達と高所順応をしてヒマラヤなどの登攀に挑むクライマーも多くいました。
けれども彼らとは身体能力も違うからそこまで先鋭的な登山はできない……自分らしいスタイルの登山って何だろうと常々考えていたんですね。
そこで巡礼登山・山岳お遍路という登山を、活動のもうひとつの柱に据えることにしたのです。
登山雑誌『ランドネ』での「神様百名山を旅する」連載は、もう10年近く続いています。
——山と神様を知るためにオススメの本は?
良い内容だけれど絶版になってしまっている本も多いのですが……。
今でも入手できるものでオススメは『日本の神様読み解き事典』。
山で出会った史跡の案内板などに記された神様のことが、すぐに分かります。事典ということで分厚く重いので、ザックに入れておけばトレーニングにもなりますよ(笑)。
日本の神様読み解き事典 [ 川口謙二 ]
発行年月:1999年10月
ページ数:560p
ISBN:9784760118243
第1編で、日本における神祇の系譜、ならびに神々・神社にまつわる基本的事項を概論として収録。第2編では、記紀神話に登場する神々を五十音順に収録し、その神の系譜・神話および神名の由来について述べる。第3編では、民俗の神様を中心にして、これに関係する神社などを五十音順に収録。別冊付録で第2編の記紀神話に登場する神々の系譜を一枚の大系図として表した「記紀神話の神々・系図一覧」がある。神名・神社の総索引、別冊付録の大系図の五十音別索引・神明番号別索引付き。『日本神祇由来事典』を縮小して普及版としたもの。

提供:廣田さん(心も満たされる登山……もっと深く魅力を感じ取るには?)
——廣田さんが思う登山の魅力って?
登山は身体を動かすスポーツですが、精神的な充足感も得られることです。
憧れの頂に立った感動やそこで出会った絶景は、心にも深く刻まれますよね。
それに加えてその山の歴史や由緒を知ってから登ることで、朽ちた石仏や文字が消えかけた石碑、果ては路傍の小さな石からも、ありがたみを感じ取ることができるのです。
試験勉強では出来事と年号をリンクさせるだけの日本史も、山やそこで活動した人物をからめることでぐっと面白く感じられるようになるんですよ。
廣田さんより、山好きのみなさん&登山を始めたい人へ

提供:廣田さん(廣田さんが伝えたい山の楽しみ方とは?)
廣田勇介ガイド|ホームページ
関連記事