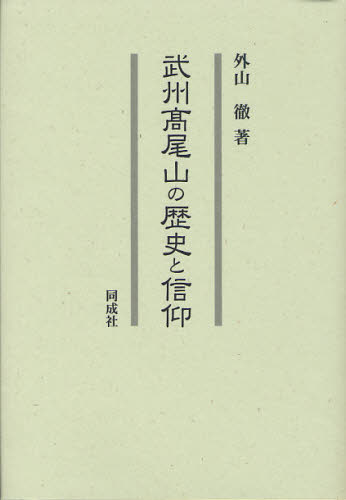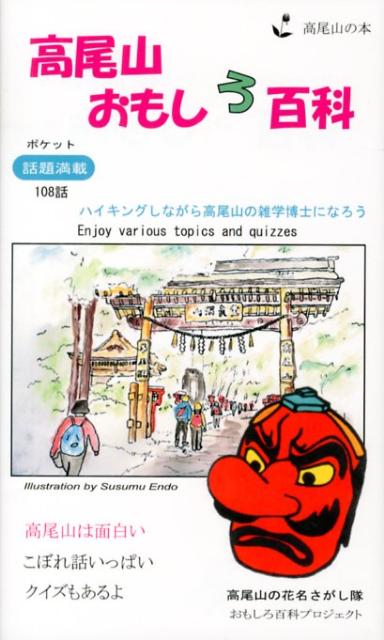時代の波にもまれながら生き延びてきた高尾山

今ではミシュランの三ツ星も獲得し、世界に知られる山となった高尾山。実は1300年以上にも渡る長い歴史があり、時に荒廃し、時に手厚い保護を受け、時に苦難を耐え忍ぶ時代に身を置くこともありました。
時代の波にもまれながら今日まで生き延びてきた高尾山の豊かな歴史について、高尾山のはじまりである開山の時より一つずつ紐解いて見ていきましょう!
開山、そして山岳信仰の山に
高尾山がいつどのように開山され、どうして山岳信仰の山となったのでしょうか。ここでは、高尾山の信仰のルーツについて紹介します。そこには、1300年に渡る長い歴史があり、高尾山が霊験あらたかな山であることを改めて感じさせられます。
744年、行基が髙尾山薬王院を開山

奈良時代中頃、仏教によって国の平安を守ろうとしていた、信仰心の篤い聖武天皇からの勅命を受けた僧侶の行基(ぎょうき)によって髙尾山薬王院が開山されたといわれています。聖武天皇は国分寺という仏教寺院を日本の各地に建立しましたが、髙尾山薬王院もその一つです。
所説ありますが、行基は民衆に仏教の教えを広め教化すると同時に、農業用水施設の建設や架橋、築堤といった社会事業をも展開し、行基菩薩として多くの人から敬われました。
1375年、俊源が荒れた寺院を復興

行基が開山した時代から600年の月日が流れた頃、京都の高僧、俊源大徳(しゅんげんたいとく)が入山し、荒廃していた寺院を現在のような華やかな寺院へと改修。薬王院ではこの俊源大徳を中興の祖としています。
俊源大徳は高尾山琵琶滝での修行により飯縄大権現の霊感を感得したと伝えられており、高尾山における飯縄権現信仰の始まりと言われています。これより以降、薬師信仰と共に飯縄権現信仰の霊山として高尾山は認知され、醍醐派(当山派)の修験道の場として発展していきます。
飯縄大権現ってなに?

飯縄大権現(いづなだいごんげん)とは、長野県にある飯縄山に対する山岳信仰が発祥といわれている神で、白い狐に乗って剣と縄を持った烏天狗(からすてんぐ)の形であらわされることが多いのが特徴です。
上杉謙信や武田信玄など、戦国時代の武将の間でも戦勝の神として篤く信仰されました。こうしたことから髙尾山薬王院の本尊は天狗であり、境内にも天狗の像がたくさんあります。
高尾山は神仏習合の山

ここまで読んで、「あれ、高尾山って仏教の山?神道の山?」とギモンに思った方、鋭いですね。実は、高尾山は行基がもたらした「仏教」と俊源が会得した「神道」が混ざり合い再構築された「神仏習合の山」なんです。
鎌倉時代から江戸時代まで、武将や幕府に守られてきた高尾山に、明治時代に危機が訪れます。それが、「神仏分離令」。神道と仏教を明確に分けるための法律で、特に神仏習合の社寺が荒らされる被害を受けました。髙尾山薬王院は「飯縄大権現」を「飯縄不動」に変え、寺院であることを訴えて被害を免れました。
今でも髙尾山薬王院の本尊は「飯縄大権現」

今でも高尾山の本尊は天狗の「飯縄大権現」で、中興の祖である俊源大徳が飯縄大権現の霊感を感得したと伝えられる時代からずっと本尊として奉祀されてきました。
髙尾山薬王院の1300年に渡る長い歴史の流れを知っておくと、お参りするときや境内で見かける天狗の像の意味が分かって、より楽しむことができますよ!
守られ続けた戦国、江戸時代
俊源大徳が荒廃した薬王院を立て直して以降、飯縄大権現を本尊とした髙尾山薬王院。戦国時代から江戸時代にかけては、時の為政者による手厚い保護を授かることができ、信仰の広がりや自然の保護など、高尾山は隆盛の時代を迎えます。
戦国時代、北条氏が薬王院と高尾の自然を保護

戦国時代になると高尾山は北条氏が治める領土に。1560年、北条氏康は髙尾山薬王院薬師堂修理のための寺領を寄進し、その翌年には八王子城主の北条氏照も寺領三千疋を寄進、さらに1578年には竹林伐採禁止の法を定めるなど、北条氏によって髙尾山薬王院や高尾山の自然は手厚く保護されることとなります。
また、北条氏以外の武将たちも戦時の軍勢による乱暴を禁止するため、制札を高尾山に下して丁重に扱い、それによって高尾山は戦火を免れています。
江戸時代、幕府からの保護により、庶民の信仰の要に

為政者が徳川幕府へと移っても高尾山の保護は踏襲され、元禄時代には常時僧侶の教育や研究が行われる常法談林所となり、江戸時代中頃には飯縄権現堂本殿の建立、1753年には現在みられるような拝殿と幣殿、本殿の三殿一体となる飯縄権現堂が完成し、高尾山は守られ続けます。
他にも、高尾山の自然保護や植林も積極的に行われました。また、普段は拝めない寺社の仏像やご神体を一般庶民や信者に対して拝観できる機会を設けることを出開帳といいますが、江戸時代には各地で出開帳が流行し、高尾山も江戸で出開帳を行うなどして庶民の信仰を取り込んでいきました。
明治時代から戦時中は苦しい時代に

明治時代には神仏分離令が発布されたことで、特に神仏融合している社寺に対して打ち壊しの嵐が日本中で吹き荒れ、髙尾山薬王院は寺院であることを強調して難を逃れます。大正時代には関東大震災の被害を、昭和4年には火災による被害を受けます。
さらに戦時中には造船のために高尾山の木々が伐採され、終戦間もない頃も家屋再建のために多くの木々が伐採されて高尾山の自然が傷つけられました。
戦後、世界から認められる山に

近代に入ってからは苦難続きでしたが、昭和25年には東京都立高尾陣馬自然公園の指定を、昭和42年には国定公園に指定され、高尾山の自然が再び守られるようになりました。平成10年には飯縄権現堂の大改修が行われ、江戸時代の極彩色の典雅な姿が再現されました。
現在では、都心から近いのに自然が豊かであることや都心からの交通の便が良いことが評価され、ミシュラン三ツ星も獲得!世界から認められる山、世界的な観光スポットとなっています。
戦後の高尾山の歴史
1927年 日本百景に選定
1950年 東京都立高尾陣馬自然公園に指定
1967年 明治の森国定公園に指定
2005年 関東の富士見百景に選定
2007年から連続してミシュランガイド三ツ星の観光地に選出
ケーブルカー、リフトにも歴史あり!
高尾山を初心者でも登りやすくしてくれているケーブルカーとリフト。縁の下の力持ちでもあるこれらの乗り物が持つ歴史を紐解いてみましょう!
ケーブルカーはいつできた?

ケーブルカーは戦前の昭和2年から営業が始まり、戦時中の企業整備令によって昭和19年に営業を一旦停止、そして戦後の昭和24年に営業を再開し、以後現在まで高尾山を訪れる人々の足となって活躍しています。
車両についても戦前の営業開始時からは随分と変化を経ており、高度経済成長期の昭和43年に全自動制御の近代的な大型ケーブルカーが導入されています。現在走っている車両は、平成20年に導入された新車両です。
リフトはいつできた?

リフトは、東京オリンピックの年である昭和39年に一人乗りのリフトとして営業がスタート。昭和46年にはベルトコンベアー式乗降装置の採用で二人乗りのリフトとなりました。子供から大人まで高尾山の景色を楽しみながら12分の空中散歩が楽しめるリフトも、既に50年以上の歴史があるんです!
ケーブルカー・リフトについて詳しく知りたい方はこちら
高尾山の歴史をもっと知りたいなら・・・
高尾山の歴史をより詳しく知りたい方は、書籍を参考にするのがおすすめです。さらに深い知識が得られます。ますます高尾山が好きになってしまいますね!
武州高尾山の歴史と信仰
高尾山の信仰のはじまりから、幕末、明治維新の時の様子までが書かれています。
高尾山おもしろ百科
高尾山にまつわる面白いこぼれ話が書かれています。子どもも大人も一緒に勉強できる内容です。
高尾山の歴史を知って、より味わい深い登山にしよう!

高尾山の深い歴史を知ることで、これまで何気なく見ていた薬王院や天狗の像、何気なく歩いていた登山道などが、長い時を経てここに在るのだと気付き、これまでとは違った見え方をするのではないでしょうか。まだ訪れたことのない人は、歴史を知ってから登ることで、普通に登るよりも様々な気付きがあって、より楽しく登ることができるはずですよ!