ハサミを使えるようになった子どもが、R2ジャケットを……

ギザギザに刻まれたR2ジャケットは「ハサミを使うことを覚えたての子どもがつい楽しくなって切ってしまった」と持ち込まれたもの。子供の成長はうれしい反面、残念な状態になったジャケットを目にしたユーザーの気持ちも、痛いほどわかる事例でした。
齋藤さん
キャンプで活躍のナノ・パフ。うっかり災難から復活
こちらはスタッフ斎藤さんの私物。キャンプに使用しているナノ・パフは、料理をするときに袖部分が熱で溶けてしまったのだとか。
ナノ・パフはキルティングのステッチに沿って当て布ができるので、同じ箇所を2回(!)も直しても現役です。「色の違いもほとんどわからない仕上がりです」とのことですが、うっかりにはご注意を!
企業としての「機能性への責任」とユーザーの「愛着」のはざまで
ところで。アウトドア用品は高い機能性があってこそ、フィールドで身を守り、本来の役割を果たすことができます。
だからこそ、「どこまで修理するのか?」の葛藤があるといいます。
例えば、機能性を高めるために縫製なしの圧着シームで作られている防水性ジャケット。
剥がれてしまった箇所を縫製して修理をすることはできるし、ユーザーもそれを望んでいます。でもフィールドで期待されるそもそもの機能を考えると、十分な機能が回復できるとはいえない場合もあります。
平田さん
こんなにある。ゴミ箱へ捨てる前にできること
まずは自分で簡単な修理をしてみる

修理に出した場合、手元に戻るまでにやはり多少の時間がかかってしまいます。そんなときにまずやってみてほしいのが「セルフリペア」。
HPでは「ドローコードの戻し方」「毛玉の取り方」のような初歩的ものから、「ジッパーの交換方法」といった裁縫難易度の高いものまで、修理手順が紹介されています。所要時間と難易度が書かれているので、それを参考に自分で直せそうか、まずチェックしてみるのも手かもしれません。
写真はショップでも販売されている「リペアシール」。シールを貼るだけ、アイロンも不要な便利アイテム。簡易的な修理になりますが、破れた箇所に貼ることでそれ以上傷が広がることを防いでくれます。
リペアセンターに修理を依頼する
今回紹介したように、自分では修理が難しいものに関しては、パタゴニアのリペアセンターにて修理を受け付けています。
「修理後の仕上がりがちょっと心配……」というひとは、修理サービス詳細内で紹介されている仕上がり見本を参考にしてみてください。見た目だけでなく機能面まで考えて、専門のスタッフが最善の方法を選んでくれるはず。
リサイクルボックスで回収。資源を最後まで無駄にしない

パタゴニアの店内には「回収ボックス」が設置されています。ここで回収したものは、製品にリサイクルされるもの、リサイクルできなくてもリパーパスされるもの、資源の無駄にならないよう責任を持って扱われます。
「消費」ではなく「所有」へ。資源を使うことの意味
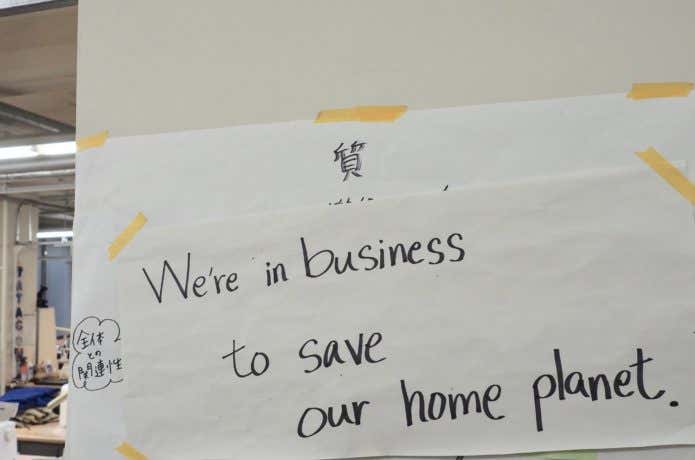
どんなアクティビティもウェアやギアが必要だし、また機能もどんどんアップデートされていきます。
新しいものがほしくなったとき、それがファッションや流行として消費するためなのか、それとも自然を長く楽しむために所有するのか、一度立ち止まって考えてみる。資源を使った製品の先には、自然フィールドや私たちの暮らしがあります。
捨てられていたかもしれない年2万点の商品がまた所有者の元へ還っていく。このことがもたらす意味を少し考えてみませんか?
Worn Wear Snow Tour開催決定!

2020年3月6日〜22日の期間、縫製スタッフを乗せたリペアトラック「つぎはぎ」が上越・東北エリアのスキー場を訪問します。縫製スタッフによる修理やセルフリペアやウェアメンテナンスの方法紹介などを行います。
パタゴニア製品に限らず受け付けているので、ぜひ見かけたら立ち寄ってくださいね。



