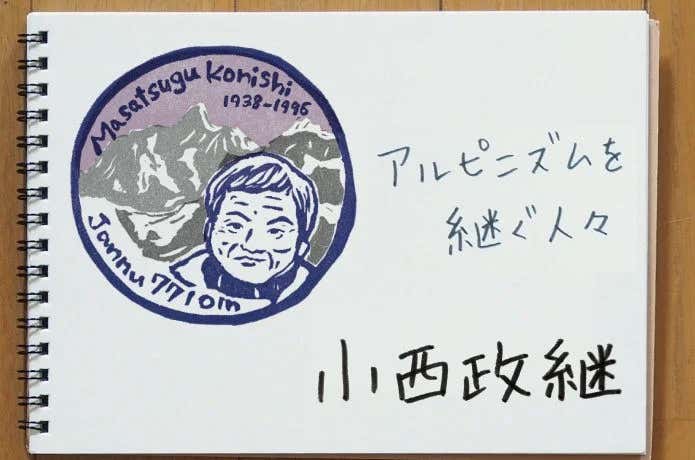小西政継:「鉄の男」がみせる人間味
第5回
いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を6人の登山家の足跡とともに考えていきます。
語り継がれる登山家、小西政継
四角くいかつい顔立ちであるが、どこかチャーミング。それは彼自身の登山歴だけでなく、仲間や後輩に与えた影響がとてつもなく大きいことにも由来するのでしょう。信奉者が多く、カリスマ性のある登山家。いまでも愛され、語り継がれています。
若くして、山学同志会へ

出典:PIXTA(谷川岳一ノ倉沢)
早くに父を亡くした小西は、高校進学をあきらめ活版印刷の会社に就職します。職場の山岳会の部長に連れられて、西黒尾根から谷川岳に登り、一ノ倉沢の岩壁に目を奪われます。クライマーたちが足しげく通う、アルパインクライミングの歴史的な場所です。この時の一ノ倉沢の残像が、小西を強く山へと駆り立てたのかもしれません。
18歳で、「山学同志会」という社会人山岳会に入ります。今でこそ、数々の名クライマーを輩出した、日本屈指の山岳会ですが、このころはまだ結成10年にも満たない、小さな会でした。
小西には、入会翌年の3月の八ヶ岳連峰にて、赤岳東壁センターリッジを登っている最中に、その難しさに耐えきれなくなり、登山靴を脱いで靴下で登ったという逸話があります。雪の残る早春の3000m近い山です。どこかスケールが違いますね。
海外の最先端を見据えて

出典:PIXTA
仕事は規則的で、帰宅し夕食を食べたら8時には就寝。朝3時半に起きて、2時間走って体力をつけていました。山にのめり込み、めきめきと頭角をあらわしていきます。
山の本については、日本語の本はもちろんのこと、海外の登山家の本も辞書を引き引き読んでいました。山のことをむさぼるように吸収していたように見えます。
小西は早いころから、視点を国内にとどめず、世界の最先端の登山を知り、座標軸を描き自分がどの位置にいるのか自覚しようとするところがありました。そのうえで、先鋭的な登山をするにはどうしたらよいのか、アルピニズムを追求する登山家でした。
ヨーロッパアルプス初見参で、マッターホルン北壁冬季第3登

出典:PIXTA(マッターホルン北壁)
山学同志会に不幸な事故が起こります。
甲斐駒ヶ岳赤石沢奥壁で3人の仲間が遭難死。小西は、彼らと、ネパールの6000m峰、アマダブラムに新ルートを開拓することを視野に入れていました。これは世界を基準に考えても難易度の高い挑戦。そのため、あきらめざるを得ませんでした。
方向転換した先は、ヨーロッパアルプス。1967年に見事、マッターホルン北壁の冬期第3登を成し遂げます。
1964年に海外渡航が自由になった直後。日本のクライマー達は、ヨーロッパアルプスの無雪期の登攀に夢中でした。しかしヨーロッパのクライマー達はすでに冬季登攀などより困難なクライミングへと向かっていました。それを読み知った小西は、国内でトレーニングを重ねていたのです。
鉄の集団を率いる登山家に

出典:PIXTA(前穂高岳から明神岳に連なる稜線、パチンコの舞台のひとつ)
小西は「鉄の男」と呼ばれていました。それは小西自身が、山学同志会を「鉄の集団」にすると発言したことに由来します。
マッターホルン北壁冬季第3登後、小西の視線はすでにその先のヒマラヤの壁を見据えていました。そのためには、絶対的な体力を素地とし厳しい登攀を続けていく力が必要だと考えたのです。
穂高連峰での夏合宿や冬季のいわゆる「パチンコ(*)」など、厳しい環境で継続して登攀する計画を立て、海外のルートを想定していきます。そして、穂高周辺の岩場を中心に、幾つもの新ルートも開拓します。
そんな厳しい顔を見せる小西ですが、ときにはハイキングや家族と山歩きをする穏やかな面もあり、山であれば何でも楽しむようなところがあったのではないかとうかがわれます。
山学同志会はこのあと、アイガーダイレクト冬季第2登やブルイヤールの赤い岩稜日本人初登、冬季初登などヨーロッパアルプスで目覚ましい登攀を繰り返しますが、小西はこれらに参加せず、すべて後進の仲間たちが登った記録です。その理由は、次にあります。
*パチンコ
冬季に、横尾にそびえる屏風岩から穂高連峰の登攀を幾つか繰り返しながら、縦走していくことを通称「パチンコ」と言う。その登攀計画を線でたどると、まるでパチンコ玉のような動きになるため。
次なる仲間たちとエベレストへ向かう
そのころ小西は、ひと足早くヒマラヤへと歩を進めます。1969年と1970年に、日本山岳会のエベレスト登山隊に参加したのです。大学山岳部育ちが中心の日本山岳会と、社会人山岳会では育った環境が違い、登山に対するスタンスや感覚も異なり、カルチャーギャップがありました。
小西はこの隊のなかで、南西壁という未踏の壁に向かいますが、登頂はなりません。一般ルートである南東稜から植村直己らが登頂し日本人初のエベレスト登頂となります。
頂きこそ極められませんでしたが、小西はここで、遠征隊の組み方や大所帯の登山のタクティクスなどを学びます。それはスタイルこそ違っても、その後小西が率いる山学同志会の遠征に大いに貢献したと思います。
怪峰・ジャヌーと世界第3位の高峰・カンチェンジュンガ

出典:PIXTA(ジャヌー)
小西が目を向けたのは、ネパールとシッキムの国境にそびえるジャヌーでした。7710mの標高、「眠れる獅子」と呼ばれる美しい山容の怪峰です。
1976年、アンナプルナなど8000m峰前半の山では、無酸素の登頂が成功し始めたころです。小西はここでも、世界の座標軸を見失うことはなく、当初から無酸素を掲げていました。
8000m峰で無酸素が行なわれるときに、時代を逆戻りする必要はない。時代を推し進めていくのが彼の姿勢です。16人の隊員のうち13人が北壁から初登攀に成功します。
1980年、山学同志会は、ジャヌーのすぐ近くにそびえる世界第3位の高峰カンチェンジュンガに臨みます。小西は隊長になり、自分自身が登頂することはありませんでしたが、鈴木昇己、川村晴一、坂下直枝ら6人が無酸素で登頂します。
鈴木は、いまでも現役の国際山岳ガイドとして、日本の登山界をけん引する重鎮のひとりです。坂下は、後述のチョゴリ北稜のサミッターでもあり、現在はクライミングギアなどの輸入会社・ロストアローの社長です。
登山隊をオーガナイズする手腕を起業へ

出典:wikimedia commons/Kuno Lechner(チョゴリ北稜)
小西の登山隊をオーガナイズする手腕は、1981年のチョゴリ(K2、世界第二の高峰、8611m)北稜初登にも活かされます。
これは日本山岳協会の隊であり、小西は協会からメンバーの選定を始めとした全権を委任されており、名実ともに「オールジャパン」で臨んだ登山でした。個性豊かな実力者たちをまとめ上げるには、並々ならぬリーダーシップが発揮されたのだと思います。
1983年に、山学同志会で登ったエベレスト南西壁(小西自身は登頂ならず)を最後に、小西はいったん、登山から距離を置きます。
「山登りにうつつをぬかしておりました私たち中年男3名は、多くの方々の御協力を得まして『クリエーター9000』なる会社を創設しました」というあいさつ文が各方面に届きました。登山アウトドア用品の企画開発会社を仲間と起業したのです。
第二の登山人生

出典:PIXTA(ダウラギリ)
ふたたび山に戻ってきたのは、1994年、55歳のときです。パキスタンの8000峰、ダウラギリⅠ峰に登頂します。酸素ボンベを使い、アルピニズムから距離を置いた内容になります。
小西は、続く計3回のヒマラヤ登山において、綿密な準備とタクティクスで臨みます。若い頃、ヨーロッパアルプスやヒマラヤで激しい登攀を繰り返してきた者にとっては、お手の物だったのでしょう。一緒に登る仲間たちからは、「小西さんにヒマラヤを教えてもらった」との声が聞かれました。鉄の男は人情味があり、面倒見がよかったです。
マナスルにて消息を絶つ

出典:PIXTA(空から見たマナスル)
マナスルで、山頂間近で登頂を諦め行方不明となったのは、小西の登山人生を振り返るとあっけない最期でした。
先鋭的登山を推し進めてきた鉄の男が、50代半ばからは、穏やかなヒマラヤ登山を再開。穏やかといっても、それはかつての登攀と比したもので、8000m峰が人間の生存を許さない過酷な環境であることは変わりありません。どんなに強い男も、不意打ちをかけられることがあるのが、山の世界の非情さなのかもしれません。
名文家が残した、山への思い
私たちがいま、小西の生き様を振り返るとしたら、彼の書物を読むのもひとつの手立てです。小西は名文家で知られていました。とくに『マッターホルン北壁』は評価が高く、自然の描写、クライマーたちの心の動きが見事に表われています。
もう一冊挙げるとしたら、『ロック・クライミングの本』は、いかがでしょうか。技術書にとどまらず、そこには、彼の山に向かう姿勢がありありと表われています。だからこそ、技術や装備が日進月歩の現代に読んでも、価値あるものです。
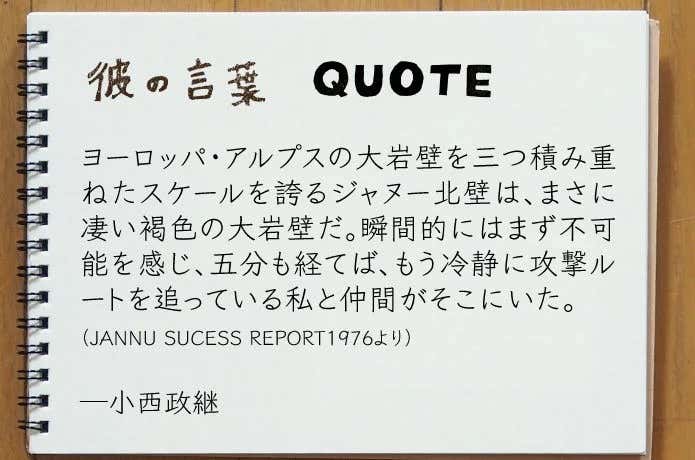

柏 澄子 Sumiko Kashiwa
登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。
中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。
Linktree: @mt.sumiko
text: Sumiko Kashiwa
illustration: Sakuya Amano
edit: Rie Muraoka(YAMA HACK)
spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)