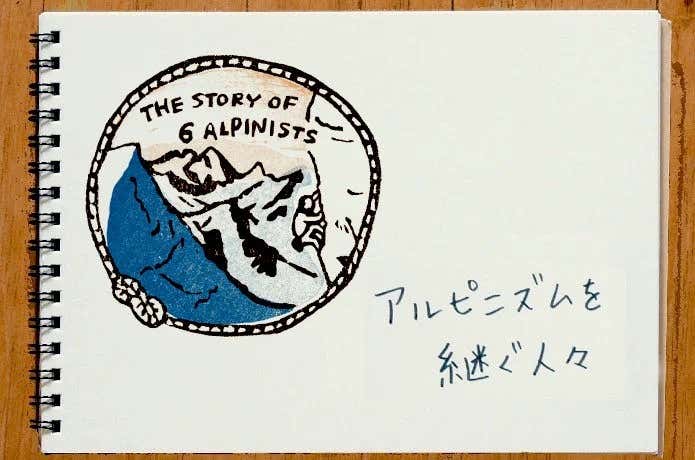未知なる山へ―「アルピニズム」の歴史をさかのぼる
第1回
山を登るということ。いまでは野外活動のひとつとして親しまれていますが、みなもとへとたどると、「アルピニズム」という概念にいきつきます。未踏の峰におもむき、より厳しい環境を求めることを指すこともあれば、精神性を含めて語られる「アルピニズム」とはいったい何か?この連載ではその歴史を7人の登山家の足跡とともに考えていきます。
近代登山の幕開け

出典:PIXTA(山岳信仰で知られる石槌山)
そもそも大昔の人は、生活の糧を得るために山に入っていました。ヨーロッパであれば水晶採掘がさかんであり、狩猟もありました。日本でも狩猟や食物採取のために山に分け入る人たちがいました。また、日本には山岳修験道の歴史もあります。山岳修験道は、山を歩く行為そのものが、信仰です。
一方で、「近代登山」という言葉があります。これは、生活や宗教のために山に登るのとは一線を画します。スポーツとしての登山、自分自身の歓びや愉しみのための登山であり、いまの私たちと同じです。
スポーツとしての登山のはじまり
近代登山は、1786年にJ・バルマとM・パッカールが、フランスとイタリアの国境にあるモンブラン(4810m)に初登頂したことで、幕を開けます。ヨーロッパ大陸の最高峰であり、シャモニーの街から望める山です。この登山は、ド・ソシュールという科学者による懸賞金稼ぎという側面もありました。けれど歴史を振り返ると、これを機に「スポーツとしての登山」が始まったのは明らかです。
登ることそのものが「目的」に
登山をスポーツとだけするにいささか違和感があるかもしれません。登山には厳格で詳細なルールがあるわけではなく、精神性や文化面も大きな要素ですね。登山そのものを目的とした行為といえばよいかもしれません。
いまとなっては当たり前のことかもしれませんが、登山そのものを目的とし、そこに充溢感あふれる行為が、これを機に、やがて今日まで綿々と実践されるようになりました。
アルピニズムの発祥

出典:PIXTA(マッターホルン)
近代登山の始まりとともに、「アルピニズム」が生まれます。
「アルピニズム」というと、アルピニストが志す崇高な思想のように語られます。それは「アルピニズム」が成熟していく過程で形づくられたもの、およびその後の歴史的評価であり、「アルピニズム」の起源をさかのぼれば、ヨーロッパにそびえるアルプスの峰々を登るときに求められた技術、行為を指すという、極めてシンプルなことです。
アルプスには氷河があり岩壁があり氷雪壁があります。これらを登攀する技術=「アルピニズム」でした。近代登山が幕を開け、数えきれないほどのアルピニストが山へと向かいます。
アルプスの登山は当初、山岳ガイドを引き連れたイギリス人の活躍が目覚ましかったです。アルプスの主だった山のほとんどの初登頂がイギリス人によってなされました。1854年のヴェッターホルンから1865年マッターホルンまでの初登頂記録が生まれた時代を、「アルプス黄金時代」と呼びます。
アルプスの金から銀の時代へ
やがて4000m級の未踏峰がなくなると、岩壁などより難しいルートや厳しい冬の登山が行なわれるようになります。 ガイドレス登山、あるいはガイドとして名を成すクライマーたちが自分自身のために登る登山も盛んになります。「アルプス銀の時代」です。
このような過程のなかで、登山家たちは、より困難な、よりシンプルな登山へと傾倒していきます。登山における美学が追求されるようになり、「アルピニズム」という思想が形作られていきます。
未知なる山・ヒマラヤへの挑戦

出典:PIXTA(アンナプルナへの道)
アルプスの登山家たちは、やがてその関心をヒマラヤへと向けていきます。困難性を求める「アルピニズム」の思想からしても、また未知なるものへの好奇心という人間の根源的欲求からしても、ごく自然な流れです。
ヒマラヤでは、1950年にフランスのモーリス・エルゾーグとルイ・ラシュナルがネパールにそびえるアンナプルナに初登頂します。8000m峰における初めての成功です。このときから14年の間にヒマラヤ8000m峰14座すべての初登頂がなされ、「ヒマラヤ黄金時代」が幕を閉じます。
ヒマラヤで成熟する「アルパインスタイル」
しかし、そこはアルプスの登山史と同じ道をたどるわけで、ヒマラヤにおいてもより困難なスタイルが求められます。
酸素ボンベを使わないこと、大掛かりな登山ではなく少人数でワンプッシュによる登頂、より困難なルート、厳冬期の登山などです。
そのような流れのなかで、フィックスロープや酸素ボンベに頼らず、極力シンプルなスタイルで、ベースキャンプからワンプッシュによる登頂を試みるスタイルを、「アルパインスタイル」と呼ぶようになりました。
ちなみに、「アルパインスタイル」の対となるのは、「ポーラメソッド(極地法)」であり、ベースキャンプからハイキャンプを複数回往復しながら、荷揚げをし、高所順応を試みながらコマを進めていくタクティクスです。
舞台をヒマラヤに移しても、いまもまだ「アルパイン」という言葉を使うのだから、やっぱり登山の歴史の始まりは厳然としてアルプスだからかもしれません。
日本特有の環境が育んだ、日本のアルピニズム
「アルピニズム」は、本場アルプスの登山を経験した日本人によって、あるいは来日したアルピニストたちによって、日本にももたらされます。
しかし、日本の山には最近発見された「氷河」はありますが、いわゆるヨーロッパアルプスのように氷河技術を要することは、まれです。ところが、信じられないほどの豪雪や人の営みが決して及ばない奥深い山岳地帯など、日本独特の厳しい自然環境があります。日本にわたってきたアルピニズムは、日本の色で広まっていきます。
アルピニズムを継ぐ人々

出典:PIXTA
ところで、はたしていまの時代「アルピニズム」という言葉は生きているのでしょうか。「アルパインクライミング」「アルパインクライマー」という言葉はあります。けれど、ヨーロッパで生まれ育ったアルピニストたちの多くがこの世を去り、時代は移り変わり、登山の様相も変化しました。
この連載では、ヨーロッパで生まれた「アルピニズム」がヒマラヤへ、日本へと渡るなか、時間軸と地勢的広がりをたよりに、各地で歴史を刻んだアルピニスト、登山家たちを取り上げます。人生を山にかけたチャーミングな彼らを通して、近代登山の幕開けとともに芽生えた「アルピニズム」とはなんであるか、己のために登る登山とはどんな行為なのか。そんなことを感じてもらえるような物語を紡いでいきたいと思います。
そして最後には、いまの現役クライマーに登場いただき、いまの時代も「アルピニズム」は活きているのか、この先登山という行為はどこへ向かうのか、語ってもらいたいと考えています。

柏 澄子 Sumiko Kashiwa
登山全般と山岳地域のあれこれをテーマにしたライターであり、登山ガイド。
中学1年生のとき、モーリス・エルゾーグの『処女峰アンナプルナ』を読み、空を見上げて雲を眺めては、「ヒマラヤはあれぐらい高いのかなあ」と妄想したのが、山登りに興味をもったはじまり。
Linktree: @mt.sumiko
text: Sumiko Kashiwa
illustration: Sakuya Amano
edit: Rie Muraoka(YAMA HACK)
spacial thanks: Makoto Kuroda(portrait)