赤岳で雪山ステップアップチャレンジ

雪山ステップアップチャレンジをサポートする企画第3弾。1月下旬に、厳冬期の赤岳へ2泊3日で行ってきました!
参加メンバーは、読者代表の内山舞さん(写真右から2番目)、THE NORTH FACEマーケティングの中村真記子さん(写真左)、YAMA HACK編集部の荻原枝里子(写真右)。
一行を赤岳山頂まで連れて行ってくれたのは、山岳ガイドの馬目弘仁さん(写真左から2番目)と、サポートガイドの鳴海玄希さんです。山岳ガイド1名につき最大2名でロープ確保するため、3名のメンバーにガイド2名で赤岳を目指しました。
天候に恵まれ、冬の赤岳登頂に無事成功!

【計画編】、【準備編】で学んだことをもとに、各々が準備を万端にしてその日を迎えました。
幸運にも晴天&微風という天候に恵まれ、赤岳登頂は無事成功!

しかし、今回は天気も良かったし準備もしっかりできていたので、景色を楽しむ心の余裕をもちながら歩くことができてよかったです。
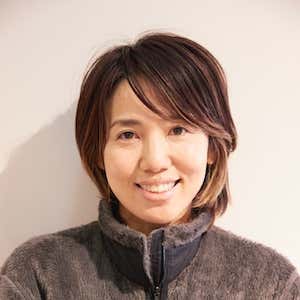


実際に歩いた行程はこちら

【計画編】で予定したとおり美濃戸口から入り、赤岳鉱泉に1泊して赤岳を目指しました。
今回は天候予備日を設けていたので2日目に赤岳へアタックした後、赤岳鉱泉まで戻ってさらに1泊しましたが、体力があればそのまま泊まらずに下山も可能。
天候の状況、自分自身やメンバーの体力を考慮して、泊数を調整しましょう。
では、実際に歩いた行程をお届けします!
≪1日目≫
美濃戸口~(南沢ルート)~行者小屋~赤岳鉱泉
≪2日目≫
赤岳鉱泉~行者小屋~赤岳~行者小屋~赤岳鉱泉
≪3日目≫
赤岳鉱泉~(北沢ルート)~美濃戸口
一番の難所は「山頂までの稜線歩き」と「地蔵尾根の下り」

今回の行程における難所のひとつは、「文三郎尾根分岐」から赤岳頂上までの道。「文三郎尾根分岐」とは行者小屋から伸びる文三郎尾根と、赤岳と阿弥陀岳をつなぐ主稜線が交わる尾根上の分岐点です。ここからは斜度もきつくなり、風も強くなります。
雪のコンディションによっては、滑落の危険性が非常に高まる場所なので、一歩一歩、アイゼンの爪を確実に突き刺しながら進むことが肝心です。

もうひとつの難所が、赤岳展望荘から行者小屋へ下る「地蔵尾根」。
こちらも斜度があるうえ、クサリやハシゴ、岩が露出している箇所をアイゼンで歩く場所があるので、バランスを取りながら慎重に!
アタック当日、山頂では快晴だったものの地蔵尾根を下るころには雲がかかりはじめたので、黙々と下山しました。

ロープでつながっていても自分でしっかり歩く意識を

滑落のリスクに備え、文三郎尾根の途中からロープをつなぎ始めました。
頼れるガイドに確保されて安心感が得られることは確かですが、油断は絶対にNG!自分が滑落することによって、ガイドや他のメンバーを危険にさらすことになります。
メンバーのひとりひとりが、アイゼンとピッケルを適切に使って、「滑落しない」歩行を行うことが大切です。

こんなコンディションだったら撤退してたかも?

今回は好条件が揃っていたので、予定どおりに歩き通すことができました。
しかし、「気温が低い」「風が強い」「降雪量が多い」「雪面が凍結している」など、困難な条件がいくつか重なっていれば、撤退やコース変更を余儀なくされていたかもしれません。

経験を重ねるしかない部分もありますが、判断に自信がないという方はぜひ、私たちガイドを頼ってくださいね。
体力を温存することが成功の秘訣
より多くの装備を使い、低い気温の中歩く雪山登山。さまざまなリスクを回避するため、変化する天候を判断するためにも体力を温存しておくことは非常に重要です。
体力を蓄えつつ登るための歩き方や休憩の取り方でもコツがあります。
●身体の向きや足の置き方を少しずつ変えて、使う筋肉を分散

雪山登山では、夏山用よりも重い雪山用の登山靴+アイゼンを装着して歩行するため、無雪期と比べると体力の消耗が早まります。
そこで馬目さんに教わったのは、足首やヒザをうまく使って、身体の向きや足の置き方を少しずつ変えながら歩く方法。少し意識しながら歩くだけで、筋力や体力を温存することができます。

●適切なスピード配分とこまめな休憩

1日目のアプローチの段階から、2日目のアタックに体力を残すための歩き方の工夫が必要です。
大切なのは、ほどよいペース配分で歩くことと、こまめに休憩を取ること。
汗をかかないためにも、意識しながら歩きましょう。





















