単なるアプローチシューズにあらず!?ヤルテクノGTXのポテンシャル
重い荷物を背負って長時間歩行する登山、ましてや足場が不安定な岩稜帯の場合はトレッキングシューズのスペックはかなり重要な要素。
そんな中で現在ひときわ注目されているのがイタリアの人気ブランド・モンチュラの「ヤルテクノGTX」です。数多くの登山雑誌で取り上げられ、登山用品店でも特設のコーナーを設置している店舗も。
短期縦走や岩稜登山でも注目の「ヤルテクノGTX」

「ヤルテクノGTX」は元々、フリークライミングを楽しむクライマーが岩場(ゲレンデ)でクライミングシューズに履き替えるまでの道のりで使用する“アプローチシューズ”として開発されました。
しかしながら、比較的軽量な装備を背負っての短期縦走や岩稜登山にも適したスペックで、クライマーだけでなく登山者にも愛用者が急増中。

その人気の裏には
*フィット感にこだわって独特な工夫を凝らしたアッパー
*推進力・グリップ力・衝撃吸収性を兼ね備えたソール
*片足約470gという軽さ
などの特徴が挙げられます。そこで実際に岩稜登山でそのポテンシャルを体感してみました。

今回「ヤルテクノGTX」を履いて向かったのは中央アルプス・宝剣岳(2931m)。
*高原バス・ロープウェイと乗り換える千畳敷カールまでは舗装路やコンクリート製の床
*千畳敷カールから稜線までは階段や石畳も点在する歩きやすい登山道
*稜線上は鎖場も点在する岩稜帯の登山道
と足元のコンディションが変化するため、様々な状態の路面(登山道)で検証することができました。
アッパー|アプローチから登山中まで変わらない「快適なフィット感」

前述の通り、様々なコンディションの路面を歩いてみて実感したのは、「しっかりフィットしつつソフトな履き心地」がどのシーンでも実感できたこと。まずはアッパー部分に着目して、その理由を検証します。
シーンによって締め具合が調整可能なシューレース(靴ひも)

「ヤルテクノGTX」のシューレース(靴ひも)には、“デュアルゾーンレーシングシステム”を採用。上写真の赤丸で囲った部分にストッパーが付いており、爪先側と足首側に分けて締め具合を調整することが可能です。
畳での正座や和式トイレでの生活が習慣化しており、足首の可動域が広い(※注)日本人。
靴ひもは登りでは少しゆるめ・下りではしっかり締めるのがセオリーですが、このシステムによって爪先はしっかりフィットさせながら、足首部分でこの調整が容易に。
登山前・登山後の移動中は爪先部分もゆるめることで、快適に過ごせますね。
足首の動きやすさとホールド感を両立したシュータン(靴のベロ)

通常の靴の場合、シュータンは前方中央部に位置していますが、「ヤルテクノGTX」のそれはシューズ内側と一体化しており、足首のホールド感がアップしています。
登りの段差で次の一歩を踏み込む時に、足首を少し曲げる動作をスムーズに行うことが可能。かといって曲げすぎてしまって足首に負担がかかるような不安は一切なく、しっかり足首が包み込まれている感触で歩行できたのです。
足全体の「動きやすさ」が考え抜かれたアッパーの形状

通常のシューレース(靴ひも)は左右並行に配置されていますが、「ヤルテクノGTX」はピンク矢印の通り、内側から外側に締め上げる左右非対称型の配置。水色矢印の通り内側にラウンドした爪先部分と相まって、足全体をナチュラルに包み込みます。

また平地での歩行時や段差では足首を曲げたり足裏を反らせたりする動作が伴いますが、黄緑色部分にスリットが入っておりアッパー全体が適度にこの動作に追従してくれるのです。
ソール|岩稜帯で発揮される「抜群の安定感」

アッパーに続いてソール部分を見て行きましょう。前述の通り、今回のルートはセクションによって足元のコンディションが変化します。
それぞれのシーンで、どのようなポテンシャルを発揮したのでしょうか。
柔らかくラウンドしたソールで推進力アップ

上の写真の通り「ヤルテクノGTX」の爪先はラウンドして少し地面から持ち上がっている、トレランシューズなどにも多く見られる形状。このため平坦な登山道や舗装路では適度な推進力が付き、テンポの良い歩行が可能です。

またソール全体がいわゆる重登山靴と比べて柔軟性があるため、岩角や階段に爪先を置いて体重をかけると適度にしなってくれます。これも、次の一歩を踏み出す際の推進力アップには効果的でした。
岩稜帯では抜群のグリップ力を発揮

もちろん岩稜での行動のために開発されたシューズ。柔軟性があるからといってスリップへの不安はありません。メガグリップコンパウンドという軟度の高いVibram®︎製の独自のパターンのソールはグリップ力抜群。

かかとから爪先までを岩の上に接地させて歩行する“フラットフッティング”を実践すれば、一見すると滑りやすそうな一枚岩もソールがしっかりとらえてくれます。
狭い足場でも安定して行動可能

鎖場やハシゴなどの難所がある岩稜では、小さな岩角のような狭い足場しかなく“フラットフッティング”が実践できない場所も。
「ヤルテクノGTX」のソールは爪先に広めのクライミングゾーン(溝が小さく接地面が大きい部分)があるため、爪先だけしか乗せられないような狭い岩場でも安定感のある登降が可能でした。
3層構造のミッドソールで下山も快適
下山は標高差255mの岩がゴロゴロした急坂を0.9km・50分で一気に下降するルート。緊張感を強いられる岩稜での行動を終えて疲れも出始める時間帯、通常は下山でのショックが波状攻撃のように足を襲います。

ここで効果を発揮したのが「ヤルテクノGTX」の3層構造のミッドソール。一番上に高い衝撃吸収性の素材を採用し、Vibram®︎製のアウトソール(靴底)との相乗効果で不自然なねじれも防止してくれます。
インソールも厚めで衝撃吸収機能を備えているため着地した際のショックが足に伝わりにくく、最後まで快適に歩くことができました。
サイズ感と登山スタイルには注意が必要

2016年から販売されている「ヤルテクノGTX」ですが、2021年から防水透湿性に優れたGORE-TEX®︎ブーティーを内側に採用したことで全体的に肉厚になっています。
筆者の場合は普段25.5cm(UK7サイズ)ですが、今回はトレラン用の薄手のソックスを履いて26.5cm(UK8サイズ)がジャストフィット。試し履きをしてからの購入がオススメです。
また当然のことながらアプローチシューズという特性上、重い荷物を背負っての長期間縦走では柔軟さが足へのストレスにつながります。こうしたスタイルの登山では、より硬くハイカットのシューズが必要になるでしょう。
メーカー担当者のオススメポイントは?
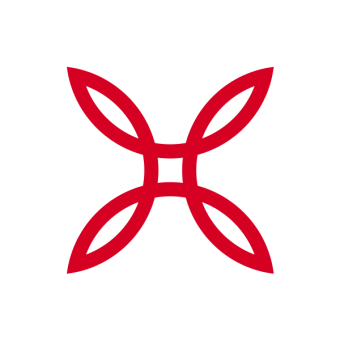
ここで、モンチュラ製品を取り扱うエアモンテ株式会社の豊田さんに、「ヤルテクノGTX」に込めたメッセージを伺いました。
ーーー「ヤルテクノGTX」の激オシポイントをひとつだけ挙げるとしたら、どんなところですか?
やはり、軽量かつ剛健なつくりがオススメです。
ーーー「ヤルテクノGTX」を使って欲しいのは、どんな人でしょうか?
「MONTURA」は特筆な機能性やデザイン性から、オーバーユースと思われている方が国内ではまだ多いブランドです。
けれども、今回の記事でもわかるように、「ヤルテクノGTX」は日帰りの岩稜登山~山小屋泊の短期縦走まで様々なフィールドで活躍するシューズ。
「MONTURA」の「ヤルテクノGTX」をはじめとしたシューズラインナップ、本格的な長期縦走のみで使用するようなイメージを持っていた方にも様々なシーンでバンバン履いて欲しいです!
コンパクトな岩稜登山にオススメの「ヤルテクノGTX」

しなやかでありながらしっかりとしたフィット感による歩きやすさと安心感、岩稜での優れたグリップ力と衝撃吸収性能を兼ね備えた「ヤルテクノGTX」。日帰りや短期縦走など荷物が軽い状態での岩稜登山では、そのポテンシャルを十分に実感できるでしょう。
日本アルプスはもちろんのこと、秋の紅葉シーズンに向けて西上州(群馬県)などの低山岩稜にもオススメ。公共交通機関を利用して山だけでなく街や乗り物でも同じシューズで行動する場合にも、快適に過ごすことができますよ。
アウトドア雑誌や登山用品店で人気を博す理由を、ぜひ体感してみてください。
今回紹介したモンチュラ「ヤルテクノ」
モンチュラ ヤルテクノ GTX
モンチュラで「ヤルテクノ」を探す









