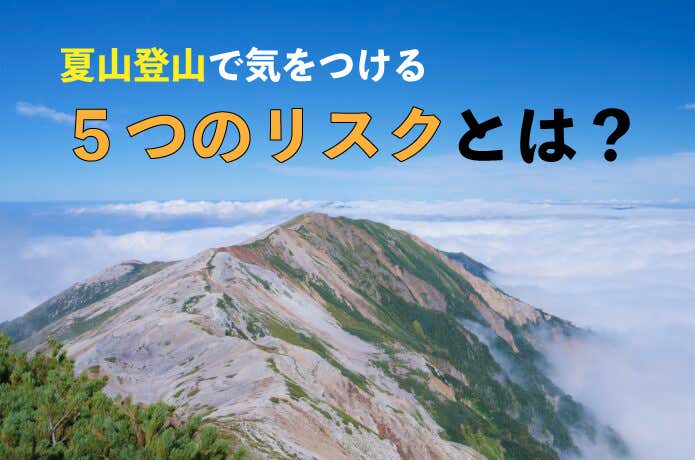みんなが登る「夏山」は意外とリスクが多い!

待ちに待った夏山シーズン。「今年こそはあの山に!」と意気込んでいる人も多いことでしょう。
雪山と異なり、誰もが挑戦しているからこそ挑戦しやすい季節に思えますが、実はさまざまなリスクが潜んでいます。いまいちど、夏山で気をつけるべきポイントを確認して、夏山を楽しみましょう。
①道迷い|遭難原因の第1位。周りをよく見よう

道迷いは遭難の原因の第1位。2位以下を大きく引き離しており、山でいちばん気をつけるべきことと言っていいかもしれません。
簡単に言ってしまえば、行くべきでない方向に進んでしまうのが原因なので、なぜそうなってしまうのかを理解することが大事です。
具体的にどんなことが考えられるか見ていきましょう。
・作業道、獣道を登山道と間違えてしまう。
・おしゃべりや障害物で分岐を見落とす。
・誤ってバリエーションルートに足を踏み入れてしまう。
・霧や日没などで周りが見えないのに無理に行動する。
・雨水の流路などが道に見えてそちらに進んでしまう。
地形図を活用して「歩くルート」を予習しておこう
まずは、足許ばかりでなく周りをよく見ながら歩くようにしましょう。
自分の足許、10mくらい先、50〜100m先や周囲を交互に見ながら歩くことで、足許の安全も確保しつつ、この先の道筋も確認することができます。対向者に早めに気づいたり、崖からの落石に備えたりするためにも大事なことです。
また、自分の行きたいルートを地図で事前に把握し、この先の道がどのようになっているか予想し、確認しながら歩くことも大事です。
たとえば上の写真のような状況。「尾根を下っていって、100mくらい下ったところで右の斜面を下りていく」と分かって歩けば、右に下りていく本来の登山道に気づきやすいですが、漫然と歩いていたら尾根をそのまま下ってしまうかもしれません。
便利なGPSアプリも活用を。ただし注意点も

落としたり電池切れになるリスクはありますが、現在地や進むべき方向を確認するのにはスマートフォンのGPSアプリも有用です。
ただし、ストラップをつけて落下や紛失に備える、予備バッテリーを持つなどして、緊急時の連絡などいざというときに使えるように対策を講じておきましょう。
②身体の不調|自身の「違和感」にいち早く気づこう
病気や疲労も五本の指に入る遭難の原因です。ありがちなさまざまな「不調」を見ていきましょう。
風邪や寝不足による「体調不良」
風邪気味や寝不足で山を歩くと、すぐにバテてしまったり注意力が低下し、ケガや事故に繋がりやすくなります。とくに早朝から行動を開始する登山では、車中泊や夜行バスでの移動など、睡眠不足になりがちです。
体調がすぐれない場合、途中で違和感を感じた場合には勇気を持って中止しましょう。山は逃げません。体調を整えて当日を迎えるのも登山のうちということを忘れずに。
炎天下を歩いて起こる「熱中症」

汗をかくことで猛暑でも体温が上がりすぎないように身体は自動調整していますが、その過程で水だけでなくミネラルも身体から出ていってしまうことで起こるのが「熱中症」です。限度を超えると手足がつったり痺れたり、めまいがしたり、頭痛や吐き気がしたり身体に力が入らなくなってしまいます。
ひどい場合には、汗もかけないくらいに水分が出てしまって身体がオーバーヒート状態になり、内臓に障害が出ることもあります。

対策方法として、帽子をかぶり、水をたっぷりとるとともに、塩飴などで塩分補給もしながら歩きましょう。熱中症の症状を感じたら、日陰で休み、水をかけて仰いだりして体温を下げ、回復を待ちましょう。
しばらく処置しても改善の兆しがない場合や、会話が成り立たなかったり頻繁にふらついたりするなどの神経症状が見られる場合には迷わず救助要請します。
急激な高度変化による「高山病」

3000m級の山々に行く人も多くなる夏山登山。ロープウェイや車でかなりの高度まで一気に上がれるような山では、身体があまり高度に順応していない状態で急激な運動を始めてしまうと、高山病になってしまいます。
高山病は頭痛や吐き気、動悸やめまい、脱力感などから始まって、食欲不振や睡眠障害などの症状があります。
意識や運動の障害があったり、脈や呼吸に著しい乱れがあれば重篤なため即救助要請ですが、そうでなければ安静にして様子を見ましょう。
ただし、昼寝は呼吸が落ちて酸素がより欠乏するので逆効果。一晩すれば回復することもよくあります。
登山口に到着したら、荷造りやトイレ休憩などに30分くらい時間をかけ、最初の数時間はゆっくりすぎると思うくらいのペースで歩くのが予防には効果的です。水分やミネラル補給も十分にしておきましょう。