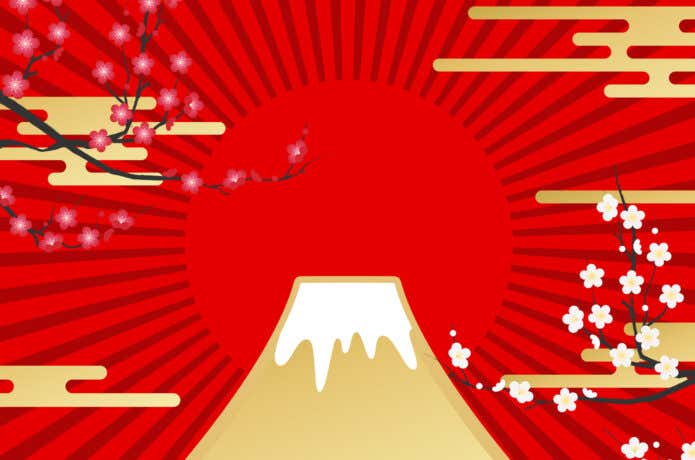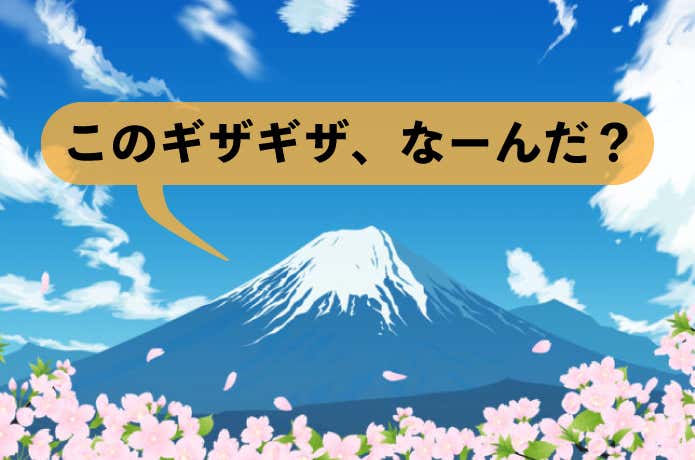【あのギザギザの正体は??!】富士山の謎は「五合目」にあり!日本一の山を解き明かそう
富士山の絵にはつい「ギザギザ」を描いてしまう。そんなことありませんか?実はあのギザギザは、みなさんが登山口として利用する「五合目」ととても深い関係があるのです。富士山の噴火の影響が及ぶ範囲や、積雪と富士山の関係など、「五合目」をキーワードに見てみると、貴方の知らない「富士山の素顔」が見えてくるかもしれませんよ!
2023/01/13 更新
-

編集者
YAMA HACK編集部
月間350万人が訪れる日本最大級の登山メディア『YAMA HACK』の運営&記事編集担当。山や登山に関する幅広い情報(登山用品、山の情報、山ごはん、登山知識、最新ニュースなど)を専門家や読者の皆さんと協力しながら日々発信しています。
登山者が「安全に」「自分らしく」山や自然を楽しむサポートをするため、登山、トレイルランニング、ボルダリングなどさまざまなアクティビティに挑戦しています。
YAMA HACK編集部のプロフィール
-

制作者
登山ガイド・山伏・応急手当普及員
田村茂樹
生き方に悩んでいた自分を救ってくれたお山に恩返ししたいと登山ガイドになる。街道歩きや里山登山からバリエーションルートや雪山登山まで幅広いフィールドを案内している。山の歴史や信仰や古道、地理・地形・地質の解説が得意。
田村茂樹のプロフィール
アイキャッチ画像出典:PIXTA
富士登山のスタート地点「五合目」の謎

出典:PIXTA(吉田口五合目)
富士山には人気のある吉田口や富士宮口をはじめとして、御殿場口や須走口、他にもいくつか登山口があります。一合目から登ることも可能ですが、多くの方は五合目から登ることでしょう。
五合目まで車で行けるのなら、もうちょっと高くまで車で行けないものだろうか。
そんな風に思ったことはありませんか。この記事ではそんな五合目にまつわる謎を解き明かしていきます。
そもそも「◯合目」はどのように決まっているのだろう?

撮影:筆者
ところで、そもそも「◯合目」はどのように決められたのでしょうか?
今ではいろんな山に「◯合目」という目安がありますが、その発祥は富士山と言われています。その意味のいわれの代表的なものをご紹介します。
・一升の米をあけた形を富士山に見立てたときに、◯合の米が積もったあたりを◯合目とした。
・登りを生涯にたとえて、山頂到達で一生(一升)、それを十に分けて◯合目とした。
・富士山は修行で登る山でもあったため、仏教で説かれる、解脱に至るまでに超えていく十の世界を各◯合目に当てた。
・登るときに道に迷わないようにお米を落としながら登り、その1合分が無くなったところを一合目と呼んだ。
では「五合目は?」というと、いろいろな紆余曲折を経て、今では車道の終点としているようです。
実はあのギザギザは「五合目」に関係あり?!
なんで五合目までしか車で行けないのか?それは車で行ける限界を五合目としているから。
では答えになっていないので、なんでその高さまでしか車で行けないのかをここから考えていきましょう。
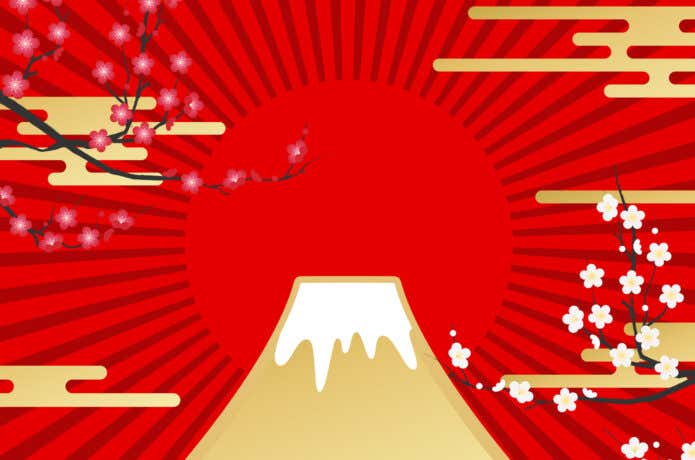
出典:PIXTA
雪の積もった富士山を描くと、イラストのように雪をギザギザに描くことが多いと思います。このおなじみのギザギザ、実は富士山の地形や五合目と深い関係があります。