
前項での準備を元に、実際に設定したルートを歩いてみました。
▼ナビゲーションの実践3ステップ
①次のチェックポイントへの角度まで回転盤を回す
②回転盤矢印と磁針が重なるまで自分が回る
③進行線の指す方向へ次のチェックポイントまで進む
コンパスを操作しながら、ナビゲーションしていく様子をみていきましょう。

“ガイド鷲尾”
ナビゲーションの手順は、チェックポイントに立ったら…3ステップを実行してみよう。地形図上で準備した情報を実際の景色にあてはめていくんだ。
“登山者Aさん”
スタート地点の高尾駅南口から①のポイントの角度は173°だから…。
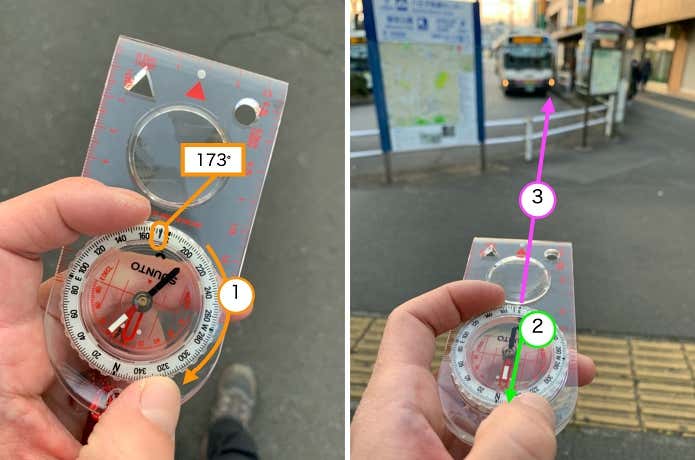
“ガイド鷲尾”
スタート地点に立ったら…
①次のチェックポイントへの角度(173°)まで回転盤を回す
②回転盤矢印と磁針が重なるまで自分が回る
③進行線の指す方向が次のチェックポイント場所なので、そちらへ進む
この後は、どんどん行くね。
写真の番号がチェックポイントの番号と一緒になっているよ。
1〜5のチェックポイント
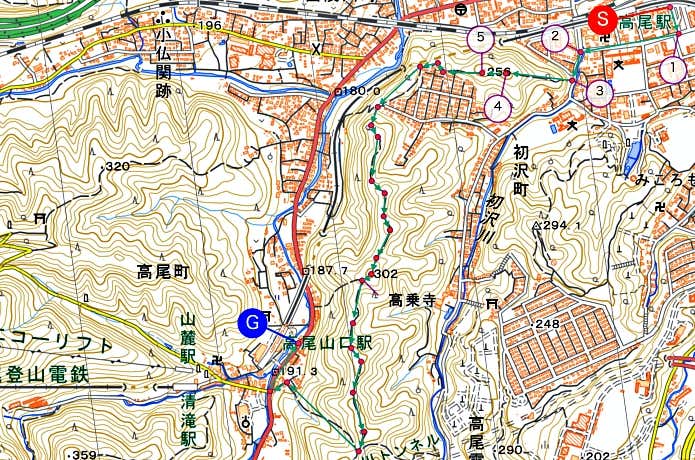





6〜11のチェックポイント
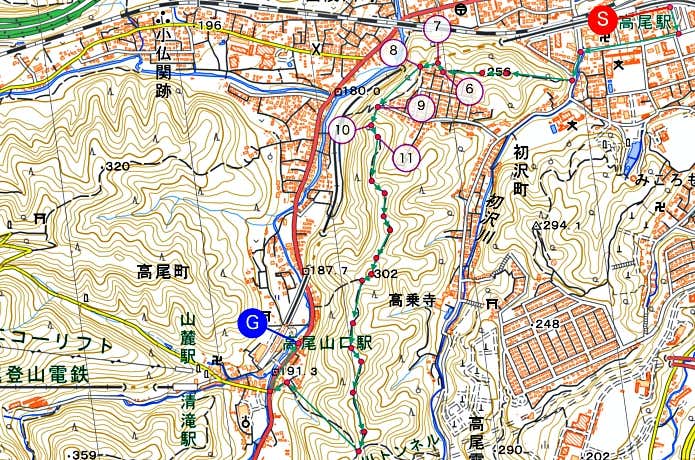
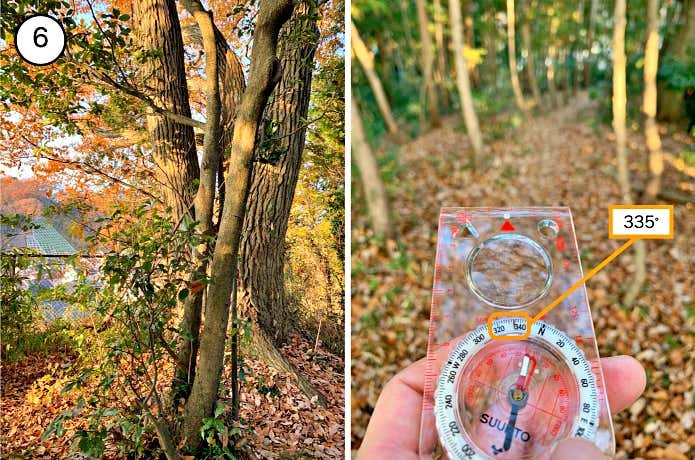

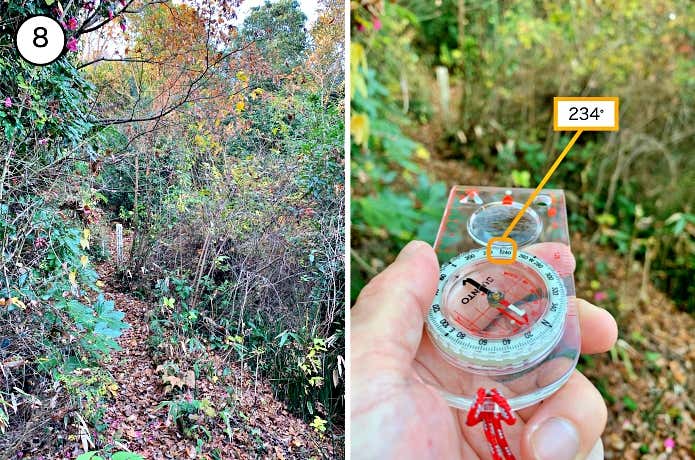


12〜16のチェックポイント
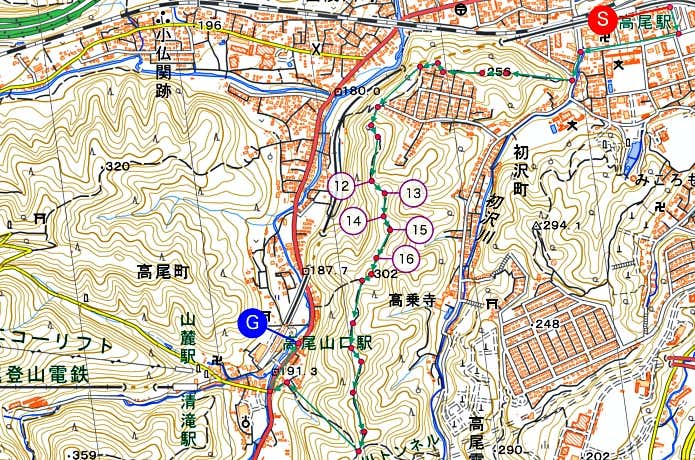

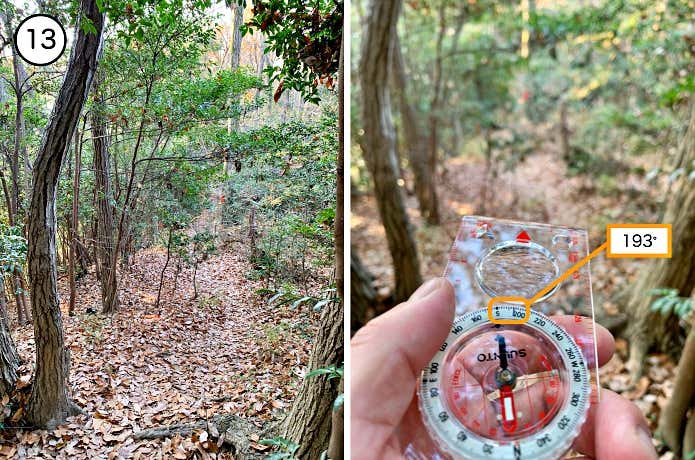
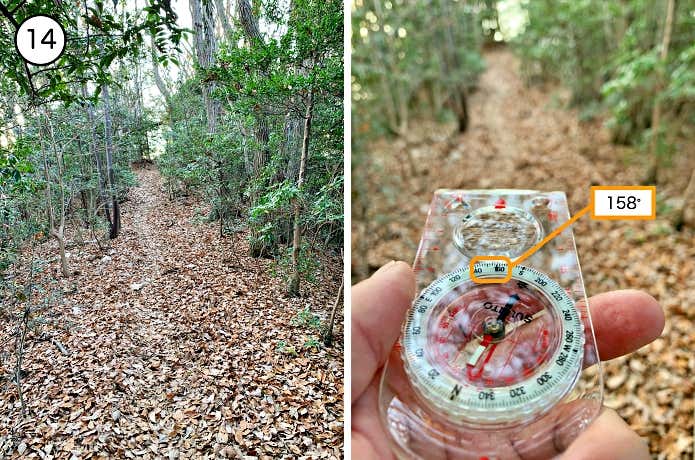

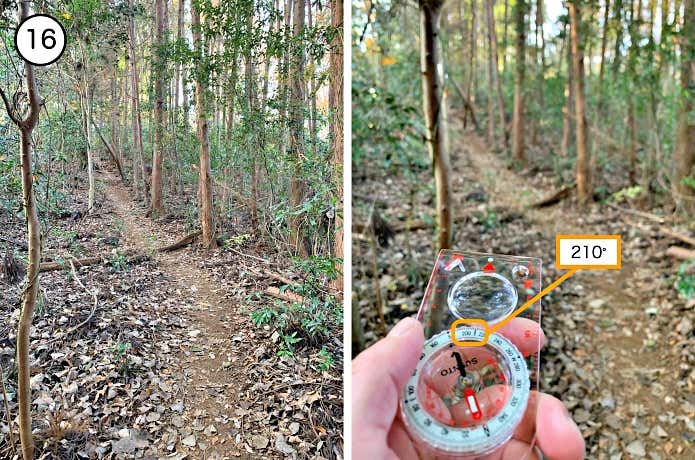
17〜21のチェックポイント
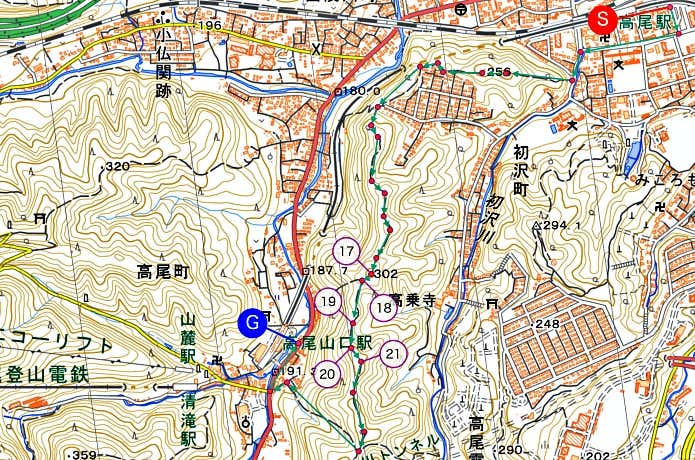





22〜26のチェックポイント
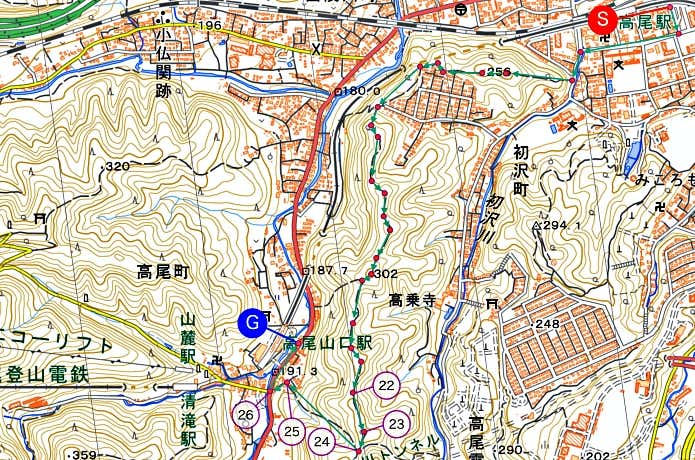






“ガイド鷲尾”
ざっとこんな感じ。
事前に調べた角度の通りに進めば、次のチェックポイントへの道につながることがわかったかな?
ただし…
事前に調べた角度の通りに進めば、次のチェックポイントへの道につながることがわかったかな?
ただし…
・チェックポイント5.ピークB(256m)の山頂が神社だった
・チェックポイント17.ピークE(302m)の先の分岐に直進するルートはなかった
とか、当日歩いてみないとわからない発見もある。
“登山者Aさん”
自分が地図上で定めたチェックポイントが、実際に自分がいる現在地かを把握することが大切だし、難しくもありますね。
“ガイド鷲尾”
ナビゲーションは、これまで学んできた等高線から地形を立体的にイメージして実際の景色と照合するという、高い技術が必要なんだ。
だから慣れないうちは…
だから慣れないうちは…
・現在地だけはGPSアプリを併用して把握しつつ、ナビゲーションする
・もしチェックポイントを通り過ぎてしてしまったら、自分が把握できる次のチェックポイントからやりなおす
というのもアリだね。
まとめ
▼ナビゲーションは地形図を見ながらの準備が大切
▼ナビゲーション準備の4ステップ
1.地形図の上に自分が歩くルートを設定する
2.設定したルート上にチェックポイントを定める
3.チェックポイント間の角度を計測する
4.ルート・チェックポイント・角度などの情報を言語化する
▼ナビゲーション実践の3ステップ
チェックポイントに立ったら…
1.次のチェックポイントへの角度まで、回転盤を回す
2.回転盤矢印と磁針が重なるまで、自分が回る
3.進行線が指す方向へ、次のチェックポイントまで進む





