シャグマアミガサタケ 3つの基本情報
1.脳みそみたいなシャグマアミガサタケ

頭部の見た目がシワシワ、脳みそのような形状をしているシャグマアミガサタケは、黄褐色・赤褐色の毒キノコです。子実体は高さ5~8cm以上で、柄は太く円柱状であり浅い縦じわを持ち合わせ、クリーム色をしています。触ると少しざらざらしているのも特徴です。
2.日本での生息地は北海道・本州

発生は早春から初夏にかけて、モミなどの針葉樹の林床に発生するキノコです。日本では、スギやヒノキの林内でも発見されたことがあります。基本的に高山地帯に多く、過去には山梨県の富士山、長野県の浅間山、福島県の七ヶ岳、千葉県の清澄山、栃木県の白根山周辺などで発生しています。
3.シャグマアミガサタケの毒成分“ジロミトリン”

シャグマアミガサタケの毒成分はジロミトリン。このまま食べても吐き気や下痢、痙攣などが発生します。
しかし、シャグマアミガサタケの恐ろしさはこれだけではありません。
煮沸することで発生する猛毒と毒抜き法
煮沸水中で猛毒に変身

毒抜き処理をすると食べられることで有名な毒キノコ“シャグマアミガサタケ”ですが、毒抜きのためにキノコを茹でると、毒成分(ジロミトリン)が加水分解されて、モノメチルヒドラジンに変化します。
モノメチルヒドラジンは揮発性物質であるため、煮沸中の水蒸気を吸うだけでモノメチルヒドラジンをも吸い込んでしまい、中毒がおきる危険があります。
モノメチルヒドラジンの症状
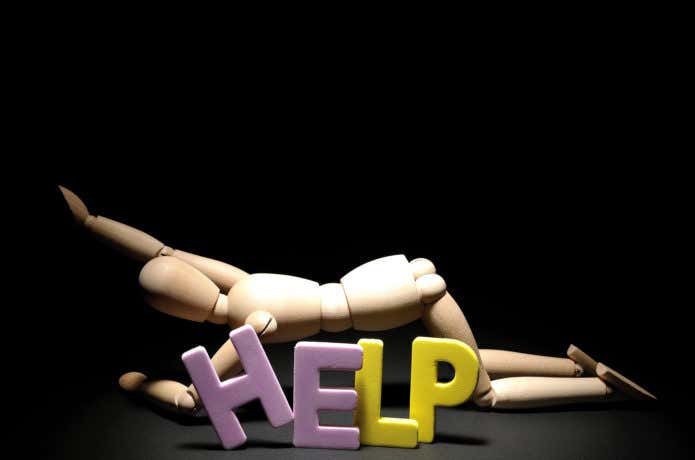
最初は胃腸系の中毒症状(嘔吐・下痢・腸痛)が現れ、のちに肝臓・腎臓に障害が現れ(黄疸・乏尿)、重症の場合は死に至ります。



