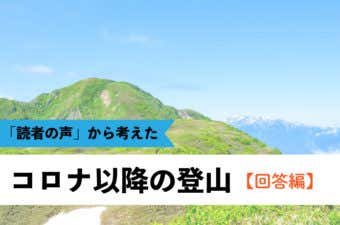山小屋のことが心配
・山小屋の運営はどの程度で赤字になるのか。
・山小屋を支援する方法は何がありますか。
・山小屋や観光地の方々の意見が聞きたい。できるだけ協力したいので。
・山小屋での密集を避けるために収容キャパを制限すると今までの料金体系では運営が厳しくなると思います。値上がりするのはやむなしですがどの程度の値上げが必要でしょうか?
「山小屋利用の可否や感染予防対策について知りたい」という声もありましたが、自粛による休業での山小屋の経営状態などを心配する声も多くありました。
登山者の「山小屋を支援をしたい」という思いは、期せずして5月18日に立ち上がった「#山小屋支援プロジェクト」「山小屋エイド基金」という2つのクラウドファンディングの総額で、約1億3249万円(7月3日現在)というかたちに実ったのは、このコロナ禍のなかでは希望ある話題のひとつだと感じます。
すべてのかたのコメントを紹介できず抜粋にはなってしまいましたが、当初の企画趣旨であった「Q&A」で簡単に答えを出せないものが多かったと感じました。それはこのアンケートの集計期間が、自粛解除間近だったことや、登山だけでなく日常生活にもさまざまな影響が大きく出ていたことなどの要因があると思われます。
一方で、登山だけでなく、日常生活においてもいままで経験したことがない「外出自粛」という特異な状況下に置かれていたなかで、モヤモヤとした思い、不安、いらだちも含め、率直に寄せてもらった「生の声」は、登山業界やアウトドア業界にとっても今後貴重な資料になると考えています。
YAMA HACKとしては、みなさんの声を届けることで役立ててもらえる関係各所にはアンケート結果をシェアしていきたいと思います。こちらよりお問い合わせください。
100%正解はない。登山を続けるため考え続けよう

おそらく、アンケートに回答してくれたかただけでなく、いまこの記事を読んでいるひとも「あぁ、そういうふうに感じてたかも」と思うことはあるのではないでしょうか?
県をまたぐ移動自粛が解除されたいま、「山に行く」ということの移動的制約はなくなったかもしれません。でもコロナウイルスは消滅したわけではなく、依然として感染者は毎日報告されています。そして、例年と大きく異なり、富士山や南アルプスといった一部山域では登山道の閉鎖なども行われ、実質的な「登山不可」となっているところもあります。
情報はつねにアップデートされ、状況は随時変わり、山行計画の変更を余儀なくされることが、コロナ以降の登山です。あらゆる情報を収集し、複合的かつ客観的に判断する。そして考え続ける。
次回の<回答編>ではみなさんの質問から、考えるためのヒントを導き出してくれるものを取り上げて見たいと思います。