ゆっくりと流れる特別な時間

深夜3時頃、結露したツェルトからひょっこり顔を出すと、そこには月明かりに照らされたマウントクックが。

空は薄明るく輝き出し、ゆっくりと流れるように夜が明けていきます。

西の谷は雲海に包まれて

マウントクックもモルゲンロートで赤く染まってきました。

日の出を満喫したところで、出発の準備を開始。今日も天気は良さそう。
「もしマウントクックに行っていたらどこにいたかな?」と、頭をかすめます。
ボールパスを後にし、入山したタスマン氷河とは反対のフッカー氷河へ下山を開始しました。
自分の技術・感覚を頼りに緊張感の続く下山を開始

下山は雪面とガレ場をひたすらトラバース(※6)していく道のりですが、ルートファインディング(※7)がかなり難しい。読図に苦戦し、一度ルートを見誤って別の谷筋を下降。途中で違和感に気づいたから良かったものの、ヒヤッとする場面もありました。

苦労しながら正規ルートを見出し、地形が緩やかになるポイントまでたどり着きました。
振り向けば大迫力のマウントクックが。タスマン氷河からの山容とはまた違った表情をしています。
何度も何度も、後ろを振り返りました。
トレッキングコースに合流!ひとまず安心も・・・

あとはトレッキングコースとの合流ポイントを目指してひたすら歩くだけ!と安心していたら・・・・
タカに襲われました。
いくら追い払っても襲いかかってくるので、最終的には私が逃げ出すことに。

ほどなくしてトレッキングコースと合流。少し休んでいると、ベビーキャリアを背負ったお兄さんが近づいてきて「ボールパス行ってきたの?!」と目をキラキラさせて話しかけてきます。
「そうですよ」と言うと「マジかよ!クレイジーだな!」とお褒めの(?)言葉をいただきました。
あとは15kmほどの舗装路を歩き、レンタカーのある駐車場を目指します。ここが本当に長かった…。
無事に下山、その時心の中にあるものは…?

日が沈み始めた頃、寂しそうにしているレンタカーを発見!
自分の力でボールパス・クロッシングを歩き切った体はクタクタながら、達成感もあります。
しかし、
マウントクックに呆気なく敗退した心の引っかかりはまだ消えていません。
「もう考えるのはやめよう」
これ以上ここにいても後腐れが悪くなってしまうので、早々に出発することに。
ひとつひとつの積み重ねが大きな達成感に

その後、いろんなトラブルに巻き込まれながらも無事に飛行機に搭乗。機内でこの山行のことを考えていました。
今回の登山は“自分にとっての大冒険”にはなりませんでした。ルート変更をした「ボールパス・クロッシング」は、確かに難しいルートではありましたが、自分の全てを出し切った山行とは言えなかったのです。
ただ、気づけばそんなモヤモヤもどうでも良くなっていました。それは、一から自分で計画し目標の山を目指したこと、このニュージーランドの出来事、全てが合わさって大きな達成感となっていたからです。
「この登山はこれで良かったんだ」ようやくそう思うことができました。
やってみないと結果はわからない。ただ、その過程は必ず経験になる
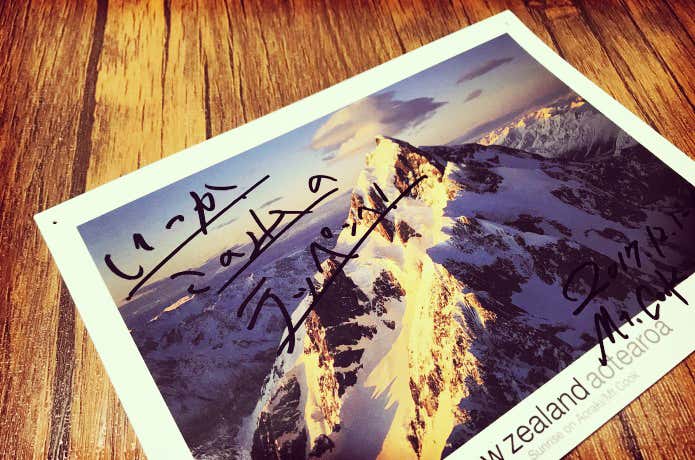
あれから2年半が経ち、私の登山に対する価値観は少し変わりました。それまでは「登山は山頂に立たないと意味がない」と考えていましたが、今はいろんな登山の楽しみ方があることを受け入れ、登山はその過程が大切だと感じるように
なりました。
それが年齢的なものなのか、生活環境が変わったからなのか、それともこの山行が影響しているのかはわかりません。
ただ、このマウントクック登山の経験があったからこそ今の自分がいる、それだけは確かなことでしょう。
今回、この記事を執筆しながらニュージーランドの地形図を眺め、「次はどうやって行こうかな」「この山いいな」そんなことばかりを考えていました。
どうやら私の冒険はまだ終わっていないようです。
きっとまたここに行くんだろうな、そんな気がしています。
今回紹介したニュージーランドの登山情報
▼ニュージーランドの地形図が見れます!日本の地形図と少し違うので、見るだけでも面白いですよ
NZ Topo Map(英語)▼ボールパス・クロッシングはガイド付きツアーがおすすめです
100% PURE NEW ZEALAND(日本語)





