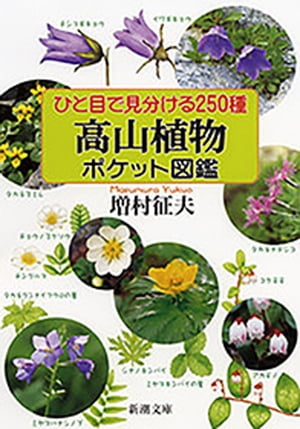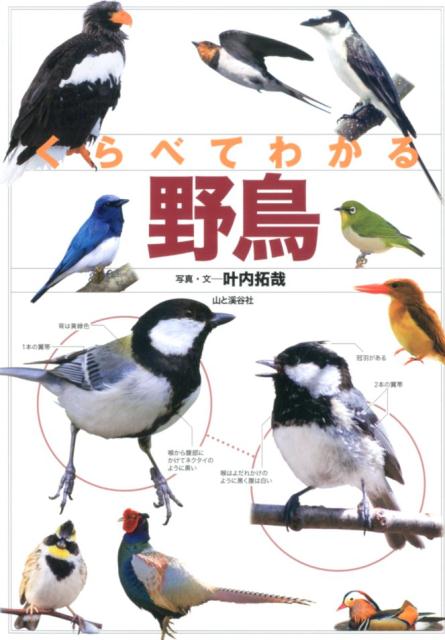山には意外な危険が潜んでいる!?

登山の道中で出会う様々な植物たち。疲れているときには、思いがけず癒されることもあるのではないでしょうか。
実は、そんな山で見かける植物の中にはとても危険なヤツが潜んでいるんです。何気なく触ったら即アウト!なんてことも。誤って触れてしまわぬように、今日は「山の危険植物」と「もしもの時の対処法」を確認しておきましょう!
パッと見は普通なのに…触れると“かぶれ”る!
登山後に帰宅してみたら、手足がかぶれていたことはありませんか? もしかしたら、触れるだけでかぶれてしまう植物が原因かも。草木が生い茂っていることも多い登山道では、気づかぬうちに危険植物に触れてしまうこともあるんです。
かぶれやすさは体質により大きく異なりますので、ここでは出会いやすさも含めた毒性などを総合的に判断した『危険度』と共にご紹介します。
ヤマウルシ(危険度★★★)

ヤマウルシの樹液に含まれるウルシオールという物質がかぶれの原因。枝を折ったり葉をちぎったときに出る白い樹液に触れるとアレルギー性の皮膚炎を引き起こす可能性があります。
ヤマウルシは羽状複葉と呼ばれる葉の形をしています。小さな葉が並んでつく軸の部分(葉軸)が赤い樹木には要注意。
ヌルデ(危険度★☆☆)

ヤマウルシと同じウルシ科のヌルデ。ヌルデは葉軸に「翼(よく)」という葉のようなものがつき、葉にはっきりとしたギザギザ(鋸歯)があります。
ヤマウルシに比べてかぶれにくいとはいわれていますが、立派なウルシ科の植物で、道端や低山の明るい林内で出会いやすい樹木なので注意が必要です。
ハゼノキ(危険度★☆☆)

こちらもヤマウルシの仲間であるハゼノキ。ヌルデ同様、低山の道沿いや明るい林内で出会いやすい種です。
ハゼノキの葉軸も赤くなるものがありますが、小葉が細く葉先がとがっているのが特徴。また、ヌルデ同様、かぶれにくいとはいわれていますが、樹液に触れないように注意しましょう。
まさに、天使のような悪魔!中身が危ない…
登山中に可憐な笑顔で元気づけてくれる花々が、実は腹黒。内に秘めた毒があるんです。なんと、みんなが良く知るあの花も!? 『危険度』と一緒に見てみましょう。
ウマノアシガタ(危険度★☆☆)

春の山野で黄色い可憐な花を咲かせるウマノアシガタ。その愛らしさとは裏腹に、茎や葉を傷つけたときにでる汁に触れると炎症を引き起こす可能性があるので要注意。写真を撮る際などは気をつけましょう。
センニンソウ(危険度★☆☆)

「仙人の髭」のような見た目が名前の由来となっているセンニンソウ。キンポウゲ科に属し、水疱や炎症を引き起こすプロトアネモニンという毒性のある成分を持っています。
この成分を逆手に取り、扁桃腺の発砲薬とし利用する民間療法もあるなど、なんとも不思議な植物です。
トウダイグサ(危険度★☆☆)

ミズバショウ(危険度★☆☆)

毒はないけど、あいたたた……トゲトゲ注意!
炎症などの症状を引き起こすほどではないけれど、触れたくない植物がほかにもあります。それは、枝や葉に鋭いトゲを持つ植物たち。気づかずにぶつかると痛い思いをすることになりますよ。『痛い度』を参考にしてみてください。
サンショウ(痛い度★☆☆)

調味料として人気のサンショウは、ギザギザの葉が目印。鋭いトゲを持っていますが、枝や葉柄の根本にあるため、トゲの数はそれほど多くありません。
ノイバラ(痛い度★★☆)

メギ(痛い度★★★)

メギのトゲは、1cm程度と長く鋭いのが特徴です。トゲが大きいので気をつけましょう。
これはタチが悪い! 油断禁物の毒針
危険植物の中には、トゲと毒を併せ持つ植物もあるからやっかいです。『危険度』が高い植物なので覚えておきましょう!
イラクサ(危険度★★★)

葉に毛のようなトゲを持つ、変わった風貌のイラクサ。このトゲに触れると、腫れと強い痛みを覚えます。
もしも、触れてしまったらどうすればいい!?

草木によるかぶれは「接触皮膚炎」と呼ばれ、刺激を起こす成分に触れた部分に、赤くなる・腫れる・水疱ができる・かゆみや痛みを生じるなどの症状が出てきます。

もしも触れてしまったら、できるだけ早く洗うこと。原因と思われる物質を取り除き、石鹸を使い接触面を水でよく洗い流します。軽いかぶれであれば数日で自然治癒しますが、症状がひどい場合は皮膚科を受診しましょう。

専用の治療薬はなく、ステロイド外用剤などで炎症やかゆみを抑えるのが一般的。かゆみが強い場合は、アレルギー用の飲み薬が処方されることもあります。
かいてしまうと炎症がどんどん悪化し、症状が進行してしまいますので、とにかく「かゆみと戦うこと」が早く治す秘訣。かゆみの緩和には、氷などで患部を冷やすことも効果的です。
登山に行くとき、予防策はある?
山には似たような植物がたくさん自生しているので、危険植物を見分けるのは非常に困難です。狭い登山道では意図せず触れてしまうことも考えられます。それでも、触れると危険な植物があるということを知っているだけでも違うのでないでしょうか。むやみに植物に触らないこと、できるだけ露出を控えることが1番です。
登山の前に、植物図鑑を見てみよう!
山では様々な植物が登山者を出迎えてくれます。たとえ危険植物であっても、自分が知っている植物に出会うとなんだか嬉しいもの。ぜひ一度、山で出会える植物の図鑑を見てみてください。登山の楽しみがきっと増えるはずです。
新潮社 ひと目で見分ける250種高山植物ポケット図鑑
山と渓谷社 くらべてわかる野鳥