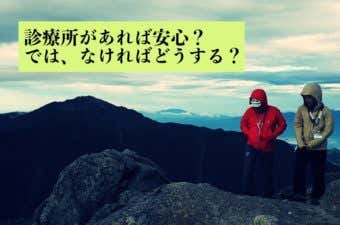アイキャッチ画像出典:PIXTA
熱中症は怖い、登山中だとなお怖い

夏に向けて登山を楽しむ人が増える反面、熱中症も増えていきます。熱中症の症状と、なぜ登山中の熱中症が増えるのか見てみましょう。
熱中症は気づきにくい

熱中症の初期段階の症状は、頭痛や発熱、めまいなど、誰もが一度は経験したことがあるような症状です。これらは、睡眠不足や疲労から起こる症状と似ていて見逃しやすく、悪化させがちなので注意しましょう。
熱中症になるとどうなるの?

熱中症は体に熱がこもって起こる異常のこと。その症状は、重症度別に熱痙攣・熱失神(軽度)、熱疲労(中等度)、熱射病(重度)と分けられます。
初期段階は、一時的な失神やめまい、立ちくらみ、体内の塩分濃度が下がって起こる筋肉痛や筋肉の痙攣です。中等度になると、頭痛、吐き気、嘔吐、怠惰感など風邪に似た症状が表れ、さらに重度になると、全身の痙攣、意識障害や錯乱、昏睡など危険な症状が出てきます。
▼重症度別の症状一覧
| 重症度 | 症状 |
|---|---|
| 軽度 (熱痙攣・熱失神) | めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗、筋肉痛や痙攣など |
| 中等度 (熱疲労) | 吐き気、嘔吐、頭痛、体のだるさ、集中力や判断力の低下など |
| 重度 (熱射病) | 体に触ると熱い、まっすぐ歩けない、足取りが不安定、意識が朦朧としているなど |
山には病院がない!

仮に山で熱中症になって救助要請しても、病院に行くまで時間がかかります。手遅れにならないよう早めの処置が大切です。
登山に潜む熱中症の3つの要因

数キロの荷物を詰めたザックを背負い、傾斜がある山を長時間歩く登山は熱中症が起きやすいスポーツの一つ。しっかりとその要因を理解しておきましょう。
【1】体温が上がりやすい

登山は長時間動き続けるため、どうしても体温が上昇します。さらに、梅雨から夏の樹林帯は風通しが悪く湿度が高かったり、稜線では日差しを遮るものがなくなり直射日光にさらされるなど、環境的要因にも注意が必要です。
【2】体温調整に必要な水分が不足しやすい

登山道は傾斜の強い上り坂を歩くこともあり、激しく動くことで息を吐く回数も増え、呼吸や汗から水分が排出されていきます。また、荷物が重くなるので水の量を抑えめにしたり、トイレに気軽に行けないので水分補給を控えたりなどしてしまい、結果、体温調整に必要な水分の不足につながるのです。
【3】体力を使うので、不調につながりやすい

早朝から行動が始まる登山は寝不足になりがち。そして、重い荷物を背負い長時間歩きます。登山での消費カロリーは『体重kg×行動時間×5kcal』(※1)で計算すると、ザックの重さを含めた4kgの荷物で、体重50kgの人が4時間歩くと約1080kcalが目安です。登山はかなり体力を使うスポーツなので、体調の変化に留意しましょう。
参考:※1 山本正嘉. 「登山の運動生理学百科」 東京新聞出版局. 2000年
登山前の熱中症対策が超重要!

登山中の熱中症対策はその日から始めるのではなく、登山前から始めるのが最善策。当日に備えて体調を整えて、登山に臨むことが重要です。では、体調を整える5つの要点を見てみましょう。
暑さになれておこう

登山の高山病予防のために高所順応があるように、熱中症予防にも暑熱順化と言う対策があります。外に出て暑さに慣れる、ウォーキングで汗をかくなど、1日のうち1~2時間を1週間程度続けると、体温調整と体液バランスが整い、熱中症になりにくい体に変わっていきます。
前日は早寝でしっかりと睡眠時間をとろう

睡眠不足のまま歩くとバテやすくなります。早朝の行動開始になるのであれば、その分早めに寝て、きちんと睡眠をとることが大切です。
涼しい朝の時間帯に出発しよう!

日差しが一番強い時間帯は12時で、10時から14時までは強い日差しが降り注ぎます。日光を浴びる時間を減らすために、日の出前や気温が上がる前の涼しい朝に行動を開始するのも対策の一つです。
ただし、暗闇での行動は視界が狭くなるなど、注意点が必要なので自分のレベルに合わせましょう。
▼日の出前の行動には必ずヘッドライトを準備しよう
朝食をしっかり食べて体力をつけておこう

早朝に行動を始めることも多い登山では、眠い目をこすりながら準備を始める時もあるでしょう。普段の生活リズムを登山リズムに切り替えるには、やはり朝食を摂ること。脳と体を目覚めさせて活動モードに切り替えます。バランスの良い朝食は疲労感も少なく、パフォーマンスアップにもつながります。
事前の水分補給も忘れずに

登山中の水分不足を想定して、登り始める前にしっかり水分を摂っておくことが大切。朝食の他に200~500mlほどの水分を摂るのが理想です。登山中の水分補給も大切ですが、事前の水分補給も忘れずに摂りましょう。
ポカリスエットパウダー 1L用
▼しっかりと水分を持って山に行きましょう
登山中は”こまめ”な対策がポイント

体力が消耗し続ける登山中は、水分補給や栄養補給などをこまめにケアすることが大切です。早め早めの行動や、登山服にこもる熱を効率良く放出する方法など、ちょっとしたケアで熱中症の対策ができます。
喉が乾く前に水分補給をしよう

登山での脱水量は『5×体重(kg)×時間(h)』で算出し、少なくとも70%~80%は補給したい量です。水分補給は、一度にたくさん飲むのではなく、こまめに少ずつ飲みましょう。ハイドレーションシステムを使うと立ち止まらずに飲めるので便利です。急に大量の水を飲んだり、水を飲み慣れていないとお腹を壊すこともあるので、注意しましょう。
さらに、水だけでなく、塩分+ブドウ糖と果糖が含まれたものを喉が渇いたと感じる前に飲むのがポイントです。少なくとも1時間に1回は水分を摂取してください。
▼ハイドレーションなら水分補給が楽ちん
▼水分補給のポイントは?
休憩は時間を決めて、疲れる前に

15分に1回の休憩をとるなど時間を決めて、水分補給と同様に疲れを感じる前に休憩をとりましょう。
▼休憩のタイミングって?
行動食で栄養補給も忘れずに

行動食は、登山中の体に必要な栄養を補給するもの。ミネラル類も摂取してミネラルバランスを保ちましょう。熱中症予防のタブレットなどで塩分を補給するのも大切。疲れが出ないように小まめに栄養補給をすることがポイントです。
カバヤ食品 塩分チャージタブレッツ
服の着脱で体温調整をしよう

登山ではレイヤリングと言われる服装の重ね着が基本。行動開始前は寒いと感じてアウターを着ても、歩き始めると暑くなります。暑いのを我慢して服を着続けると、どんどん体力が奪われていきます。登ると暑くなることを想定した重ね着をするのが大切。長袖の袖をまくる、首元のジッパーやボタンを開けるなども、体温調整の工夫の一つです。
▼レイヤリングで体温を調整しよう
吸汗速乾素材でムレを減らそう

服の中のこもった熱を発散させるために、汗を素早く乾かす吸汗速乾素材の服装がおすすめ。綿素材の服は汗で濡れると乾きにくく、体が冷えてしまいます。吸汗速乾素材は蒸れやベタつきを減らすほか、汗冷えからの低体温症のリスクを遠ざけます。
▼登山にはやっぱり吸汗速乾Tシャツがおすすめ
帽子を被って直射日光をさけよう

標高が高い場所や稜線に出ると日差しが強くなります。直射日光にさらされると頭皮は40度を越えてしまい、熱疲労の原因にもなりかねません。直射日光を避けるためには帽子を被るのが最適。熱がこもって蒸れる時は帽子を脱ぎ、蒸れを逃しましょう。
▼直射日光は天敵!登山帽子をかぶろう
日陰で快適に

日陰と日なたでは涼しさが違うので、休憩で一息つく時は日陰で休みましょう。登山コースにより休憩ポイントがない山もあるので、あらかじめ登山途中の休憩ポイントをチェックしておくと安心です。
冷却グッズで体をひんやりさせよう

暑い体をひんやりさせる冷却グッズを使用するのもおすすめ。特に熱中症対策には、首の血管を冷やすと効果的です。水に濡らすだけで涼しくなるタオルやスプレーで体温を下げるものなど、冷却グッズを上手に活用しましょう。
▼クールタオルやネッククーラーでひんやり登山を楽しもう
▼首元の紫外線対策にはネックゲイター
リーダーがメンバーの様子を確認しよう

グループ登山は、それぞれ体力が違うメンバーと登る場合もあります。登山では一番弱いメンバーに合わせるのが基本です。リーダーは、各メンバーの体調の変化に留意しましょう。特に女性がいる場合はトイレに行きたくても言い出しにくいこともあるので、リーダーはトイレ休憩をとるなどの配慮が必要です。
いざという時に備えて知っておきたい対処法

自分自身では気付きにくい熱中症は、メンバー同士で体調を気にかけて早期に異変を発見できるようにしましょう。登山中に熱中症になってしまった時は、意識があるかないかで対処方法が変わります。いざと言う時のために、対処法を備えておきましょう。
意識がある場合は水分補給と体を冷やそう

熱中症のサインが出始めたら、
・日差しを避けられる、涼しいところに移動
・水分、塩分、糖質を摂取(飲みのもが良い)
・濡らしたタオルなどで体を冷やす(特に脇の下や首の裏など血管が多く通っているところ)
・手足を濡らし仰いで気化熱で冷やす
・横になりザックなどに足を乗せて、安静に
意識が朦朧としている場合は迷わず救助要請を

意識がある場合の対処方に加え、脈拍確認と呼吸確認をしましょう。脈がない時は心臓マッサージを、呼吸がない時は人工呼吸を行います。次に、名前を呼んだり問いかけを行い、意識状態を確認。意識が混濁していたり受け答えが鈍い時は、直ぐに救助を要請しましょう!
忘れがちだけど大切な登山後のアフターケア

翌日に疲れを残さないために、登山をした後にはアフターケアをすることも大切です。登山後の栄養補給、アイシング、睡眠のポイントを紹介します。
下山後も水分と栄養補給は大切です

一日中歩き続けたあとは体に熱がこもっていたり、汗などで水分を失っています。下山後は、糖質、ミネラル、タンパク質などの栄養と水分の補給をしましょう。補給のタイミングは下山直後が最適。下山後数時間経ってから補給するよりも、下山直後に補給した方が疲労回復が早いことが分かっています。
体の火照りをとろう

下山後の温泉で熱いお風呂に入ると、体の疲労が一気に抜けていきますよね。でも、体が火照ったままでは睡眠の質が落ちてしまいます。水分補給、また温泉の水風呂や冷水シャワーを足腰にかけて、しっかりと体を冷ましましょう。
睡眠をしっかりとって体を休めよう

日光を浴び重い荷物を背負って数時間もの行動。登山の疲れは全身に及びます。登山の疲労を残さないように、睡眠をしっかりとって体を休めましょう。睡眠しっかりとると自律神経が整い、体と脳を疲れから解放します。また成長ホルモンが分泌されて、負荷のかかった筋肉を修復していきます。
熱中症対策で夏山を存分に楽しもう!

景色を見る余裕がないくらい体調が崩れてしまうなんて、せっかくの楽しい登山が台無しに。熱中症は事前の対策から始めると、暑さに負けない体になります。大自然の魅力を全身で感じて良い山行にするために、熱中症対策を万全にして臨みましょう!
■記事監修/日本登山医学会認定 国際山岳医 稲田 千秋氏