目の前で小屋が流された、すさまじい台風

―――当時から繁盛されていたんですね。そこから今の場所に移ったのはどうしてですか?
1959年の伊勢湾台風で大洪水が起こって、すべて流されてしまったんです。周辺の木々がなぎ倒され、樹林帯だったところがさら地になってしまうくらいの、本当にすさまじい状況だったようで……。赤岳山荘のおじちゃんとおばちゃんは、鉄砲水の気配を感じて急いで避難しようと外に出たところ、ほどなくして目の前で小屋が流されるのを目撃したそうです。


―――ひええ…目の前で…。それは凄まじいですね。では、今の場所になった経緯というのは?
現在の場所は赤岳山荘のおじちゃんとおばちゃんが探し歩いて、ここなら雨風の影響を受けにくいだろうということで見つけたそうです。それから半年ほどかけて周辺の残った木々をその場で材木化して、1959年に今の赤岳鉱泉が出来上がりました。私の祖父にあたる2代目(栁澤国一氏︎)が入退院を繰り返していたこともあって、その後の運営は祖母(ムツ︎氏︎)が中心となって切り盛りしていたそうです。

ただ、運営スタイルは今とは随分違っていましたよ。昔は山小屋は登山客が泊まれるだけ有難い存在だったので、サービスなんて全然行き届いていなかった。登山者は小屋に泊めてもらう代わりにじゃがいもやにんじんなんかを持参するのが当たり前で、小屋も「それくらいして当然だ!」という感じ。
客のテントを燃やす!? 「極悪非道」と言われた山小屋が一新

―――へぇ~…。今と随分印象が違いますね。きれいで食事のおいしい、今の鉱泉になったのはいつからなんでしょう?
当時の山小屋はどこもそうだったみたいですよ。大きく変わったのは3代目である父(栁澤太平氏)の頃からだと思います。23歳で小屋を継いだのですが、父は元暴走族の不良でして……。
―――ふ、不良?!!……と言いますと?
若かりし頃は剃り込みの入ったヤンキーで、山岳会やガイドと毎日のように殴り合いの喧嘩をしていた時期もあったようです。宿泊料金を払わなかったお客さんのテントを燃やしてしまった、なんて話もあります。
―――えー?!!!!! それは相当やばいですね!(笑)
かの山岳誌には「赤岳山荘 極悪非道」なんて記事を書かれたこともあるようです(笑)
このままじゃ人が来なくなる
―――ひどい言われよう!(笑)でも、そこからどうやって今の「きれい」で「おいしい」鉱泉になったんですか?
ある時、父が目覚めたんです。仕事として山小屋をやるなら「山小屋 = 食事がまずい、汚い」というイメージを一新する必要がある、と。


―――かなり思い切った方向転換ですよね。何かきっかけがあったんでしょうか?
どうやら北アルプスの小屋の話を聞いて影響を受けた部分があるようです。八ヶ岳はアクセスが良いにもかかわらず、トイレは汚い、ご飯はカレーばっかりでまずい。高いお金をとる割にサービスが全然ダメだ、という結論になったんですね。
あとは当時、ちょうど一斉に八ヶ岳周りの小屋が代替わりのタイミングを迎えていて、グループみたいなものが自然と結成されたそうで。その話し合いで「このままじゃダメだ、お客さんが来なくなる」という流れになった、という話も聞いています。以来、小屋の内装をきれいに整えたり、食事のサービスにも力を入れるようになりました。

―――赤岳鉱泉の食事といえば、やはり「鉄鍋ステーキ」! ですが、あんなに手の込んだ料理を始めたのもそういった経緯から、なのでしょうか?
ステーキが生まれたきっかけは、10数年前の家族旅行です。こういう仕事をしていると機会は少ないのですが、たまたま泊まった旅館で1人に1つずつ鉄鍋が出てきて。今でこそ当たり前ですが、それを見た父が「これ、うちでもやろう!」って言い出したんです。最初は周囲から大反対を受けたみたいですが、今では立派な看板メニューですからね。

―――旅館の食事がもとだったとは……それを採用してしまう柔軟性がすごい!
父はサービス精神旺盛で、人を楽しませることに対するバイタリティがある人でしたし、自然相手の仕事に必要な臨機応変さなんかも併せ持っていました。そういう父の工夫や努力があったから、今の赤岳鉱泉があるのではないかと思います。
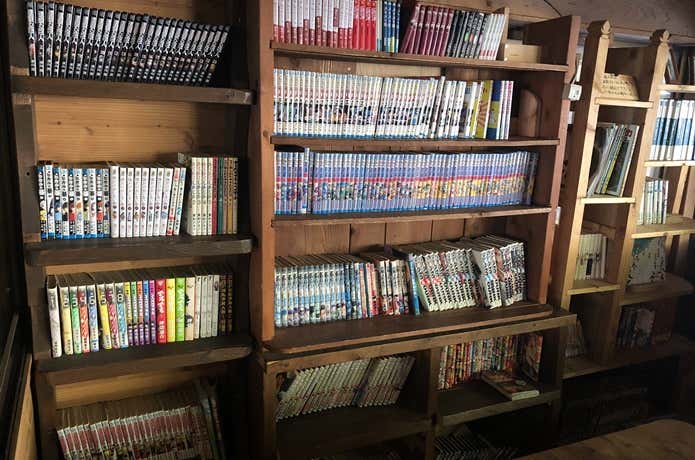
―――赤岳鉱泉のサービス精神は先代から受け継がれたものだったんですね。多くの人に愛されるのも納得です。
1つ1つはそんな大それたことではないと思いますが、父の目指した「きれい」で「おいしい」はたしかに大切にしていますね。小屋の外見はちょっと汚いんですが……(笑)
常連さんを飽きさせず、いかに心地よく小屋での時間を過ごしていただくかを念頭に日々細々したところを改良しています。
